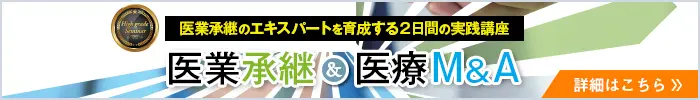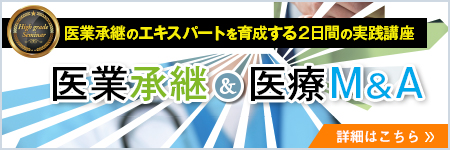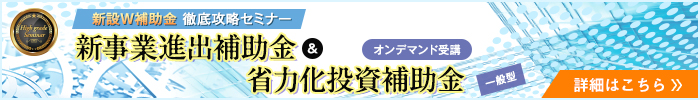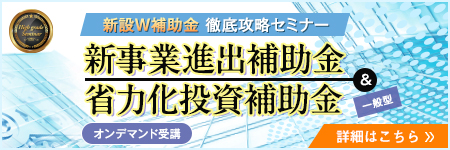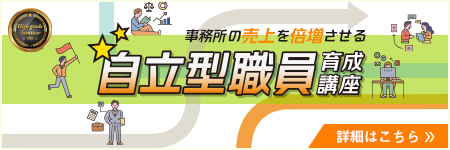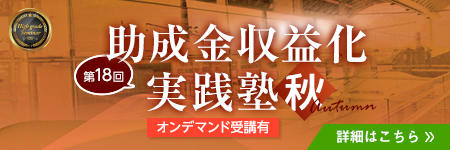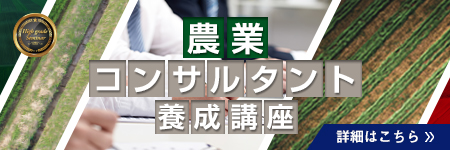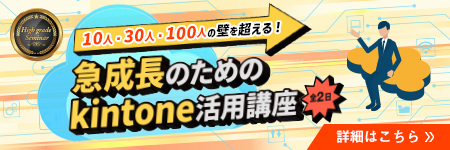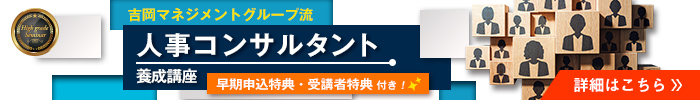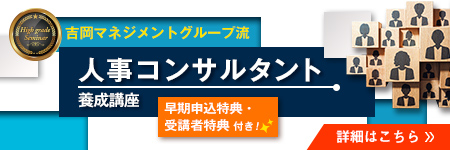無申告加算税とは?税金の内容や税率決定のポイント、無申告による注意点など詳しく解説

無申告加算税とは、法定申告期限までに申告・納税をしなかった場合に課せられる税金です。
一般的に法人の場合は、事業年度終了日の翌日から2カ月以内に法人税の申告を行い、一定の所得を得た個人の場合は毎年の2月16日~3月15日の間に確定申告を行う必要があります。しかし何らかの理由、または故意に期限までに申告を行わなかった場合、無申告の状態となるので、無申告が発覚した場合にはペナルティとして無申告加算税という税金が課されることになります。
また無申告の状態を放置したり事実が発覚したりすることで、会社や個人に様々なデメリットも発生します。本記事においては、無申告加算税について、税金の内容や税率決定のポイント、無申告により発生するデメリットの注意点など詳しく解説します。
目次
無申告加算税とは?

無申告加算税とは、加算税の種類のうち、本来の確定申告期限までに申告をしなかったとき、課税されるペナルティのことをいいます。
無申告加算税が課せられるケースには一定の条件があり、具体的には以下のような状態となったとき課せられます。
- 法律で定められた期限内に確定申告をしなかったとき
- 期限後に申告を行ったとき
- 期限後申告について修正申告や更生の請求があったとき
- 税務調査等で所得金額の決定があったとき
なお、確定申告には3つの修正方法があります。(訂正申告・更生の請求・修正申告)
以下の一覧表にて確定申告の期限前、期限後における修正方法の違いを理解しておいて下さい。
| 修正を行う時期 | 修正方法 |
| 確定申告の期限前 | ・訂正申告 |
| 確定申告の期限後 | ・更生の請求(納税額を過大または還付金額を過少に申告していた場合) |
| ・修正申告(納税額を過少または還付金額を過大に申告していた場合) |
無申告加算税と他の加算税との違い
加算税には、適用条件によって無申告加算税を含むいくつかの種類があります。過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税などです。
本章では、無申告加算税と他の加算税との大まかな違いを解説します。
- 過少申告加算税…過少申告加算税とは、確定申告した税額が実際に支払うべき税額より少なかった場合に課される加算税です。期限までに税金を払った、期限内に確定申告を済ませた、というケースでも、申告額が本来の税額より少なければ、過少申告加算税の対象となる可能性があります。
- 不納付加算税…不納付加算税とは、期限までに源泉所得税を納付しなかった場合にペナルティ的に課される税金です。ただし納付期限から1カ月を経過する日までに納付し、かつ過去1年以内で納付期限内に源泉所得税を納付している場合には課税されません。
- 重加算税…重加算税とは、事実を仮装したり隠ぺいしたりした場合にペナルティとして課される税金です。申告内容が悪質と税務署や国税庁に判断されたり、脱法行為をしたと見なされたりした場合には、上記の各加算税に代えて重加算税が課されます。
その税率(40%)からも、加算税の中では最も重い措置の税種類といえます。なお、無申告加算税以外の各加算税の税率については以下の先をご参照下さい。
無申告加算税の税率と税率を決めるタイミング
無申告加算税の税率は、本税の額や期限後申告のタイミング等によって変わってきます。また申告自体を怠っているので前述した過少申告加算税よりも重い税率となっています。
【無申告加算税の概要】
| 税額区分 | 50万円以下の部分 | 50万円超~300万円以下の部分 | 300万円超の部分 | |
| 申告のタイミング等 | ||||
| 原則税率 | 15% | 20% | 30% | |
| 税務調査による更生等の決定予知前(税務調査の実施前など) | 税務調査の通知後に申告 | 10% | 15% | 25% |
| 税務調査の通知前に自主的に期限後申告 | 5%(※1) | |||
| 重加算税 | 申告内容に仮装隠ぺいがあった場合、無申告加算税に代えて本税が課される | 40%(※2) | ||
(※1)令和6年1月1日以後に法定申告期限が来るものに対する税率(令和5年税制改正による)
(※2)仮装・隠ぺいに基づく部分に適用される税率
無申告加算税の過重及び軽減措置
無申告加算税については、上記一覧表の税率に、以下の種類別に適用要件にかなった場合、加重または軽減される場合があります。
特に下記、「短期累犯加重」「連続無申告加重」については、令和5年度税制改正において、繰り返し行われる悪質性の高い無申告行為を抑制することを目的として新設されました。なお、「短期累犯加重」「連続無申告加重」の重複適用はありません。
【加重措置】
| 過重措置名 | 適用要件 | 税率 |
| 短期累犯過重 | 過去5年以内に無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合※連続無申告過重との重複適用はなし | +10% |
| 連続無申告過重 | 前年度及び前々年度分の国税について、無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合、賦課決定をすべきと認める場合※短期累犯過重との重複適用はなし | +10% |
| 不記帳過重(所得税・法人税・消費税のみ) | 税務調査で一定の売上に係る帳簿の提出等を求められた場合不提出等であった場合帳簿の記載が著しく不十分の場合(売上の1/2以上が不記載)帳簿の記載が不十分の場合(売上の1/3以上~1/2未満が不記載) | +10%(適用要件①②の場合)+5%(適用要件③の場合) |
【加重及び軽減措置】
無申告加算税の過重及び軽減措置に関しては、特殊なケースに限り、以下の措置が適用されます。ご自分の会社並びにご自身が以下に該当していないか、十分ご確認下さい。
国外財産調書・財産債務調書に係る過重・軽減措置(所得税及び相続税)
| 過重・軽減制度 | 過重・減額割合 | |
| 過重 | 調書の提出義務を怠っていた場合提出された調書に申告漏れ(無申告)に係る財産の記載がない場合※財産債務調書については相続税を除く | +5% |
| 軽減 | 提出された調書に申告漏れ(無申告)に係る財産の記載がある場合 | △5% |
無申告加算税が不適用(免除)となるケースとは
以下のいずれかのケースに該当する場合、たとえ期限後申告であっても無申告加算税は課されません。それは無申告加算税を含む加算税が、適正な申告を怠った場合に適用される制裁的な性質を持つ税だからです。
| 正当な理由があると認められた場合 | 水害や地震等の災害、交通通信の途絶等の理由により、外形的に判断して期限内に申告書を提出できなかったことが真にやむを得ないと判断されたとき |
| 法定申告期限内に申告する意思があったと認められる場合 | ・その期限後申告が法定申告期限から1カ月以内に自主的に行われていること ・期限後申告に係る納付すべき税金の全額(本税)を法定納期限までに納付していること ・過去5年間で無申告加算税や重加算税等を課されていないこと |
参照元:確定申告を忘れたとき|国税庁
無申告加算税の計算方法と計算例
無申告加算税の計算式は以下の通りです。
無申告加算税=納付すべき本税の額×無申告加算税の税率
また上記計算式を使って算出した無申告加算税の事例は次の通りです。
なお、2023年(令和5年)までは納税額が50万円超の場合、税額は一律で20%が適用されていましたが、2024年(令和6年)1月1日以降は、令和5年税制改正に基づき、納税額300万円超の金額分には税率30%が適用されています。
納税額が500万円の場合の無申告加算税額(事例)
500,000円×15%+2500,000円(300万円-50万円)×20%+2,000,000円(500万円-300万円)×30%=1,175,000円
また税務調査前に自主的に期限後申告すると、税率が5%軽減されます。一方、申告の期限を過ぎてしまった場合、無申告加算税以外にも延滞税(※)が課されますので注意が必要です。
※延滞税とは、税の申告や税金の納付が決められた期限までに行われなかった場合に、延滞の日数に応じて日割りで計算されて課される税金の種類です。
無申告の注意点とは?

法人税や所得税の申告を行わなかった場合、追徴課税として無申告加算税が課されるだけでなく、当該の企業や個人事業主に色々なデメリットが生じます。
それは加算税という金銭的なペナルティにとどまらず、様々な点で事業をする方々にマイナスに効いてきます。
仕事が忙しいからと無申告を安易に考えず、無申告によるデメリットを十分理解した上で、常に注意して必ず法定期限までに申告を済ます心がけが必要です。
赤字欠損金が繰り越しできなくなる
青色申告事業者の場合、無申告の回数を2年連続で繰り返すと、税務署により青色申告が取り消されます。すると青色申告に係る税務上の様々な優遇措置が受けられなくなるので注意して下さい。
特に影響があるのが、赤字欠損金の繰り越し控除が認められなくなる点です。
赤字欠損金の繰り越し控除が認められると、仮に赤字になっても個人事業主で3年間、法人は10年間、赤字を繰り越しして損益通算できるので、税金支払いを少なくできます。
しかし逆に青色申告の権利が取り消しされたなら、繰り越し控除ができなくなり、税負担が増加する可能性が出てきます。
金融機関から融資が受けられなくなる
金融機関から融資を受ける場合、一般的には税務署に提出して認められた決算書や確定申告書が審査書類として提出を求められます。
しかし無申告の場合、法人・個人事業主等の業績が正しく評価された証明書が出せないので、金融機関の融資審査が通れなくなる可能性が高くなるどころか、多くは受付段階で門前払いされてしまいます。
さらに融資では、審査の必要書類として納税証明書を要求される場合もあるので、無申告では納税証明書も取れず、さらに融資が受けられないリスクが上がります。
社会的信用に傷が付いて取引に支障が出てくる
無申告だと、会社や個人事業主の社会的信用に傷が付いて、日常の取引に支障が出てくる可能性があります。
無申告を放置していると会社等に税務調査が入り、その結果、無申告加算税や延滞税を課されてしまうと、それが悪いうわさとなって取引先や金融機関に流れ、最悪、取引が中止されたり、金融機関からの融資が引き上げられたりします。
社会的な信用を失ってしまうと、事業の継続が難しくなるので、申告を放置したり税務署の告知を無視したりする行為はくれぐれも慎むことが大事です。
まとめ
無申告加算税について、他の加算税との違いも踏まえ、その概要や税率決定のポイント、課された場合に起こるデメリットから注意する点など、詳しく解説しました。
法定期限までに申告を行わず税金を納めていない状態を無申告といいます。意図するしないに関わらず無申告の状態を続けていると、最終的に税務当局からペナルティとして無申告加算税が課されます。
さらに無申告の状態を続けていると、税務調査を受けたり、調査の結果、悪質と判断されたりして、重加算税という最も重い課税措置を受けてしまうリスクもあります。
これまで申告をしていなかった期間がある場合には、無申告加算税による本来不要な税負担を避けるためにも、また無申告によるデメリットを受けないためにも、態度を改めできるだけ早めに申告を行うことが必要です。
 オンライン研修・eラーニング
オンライン研修・eラーニング
e-JINZAIで
社員スキルUP!
- e-JINZAI for account(会計事務所向け)
- e-JINZAI for business(一般企業・団体向け)
- 今ならe-JINZAIを2週間無料でお試しいただけます!

税理士.ch 編集部
税理士チャンネルでは、業界のプロフェッショナルによる連載から
最新の税制まで、税理士・会計士のためのお役立ち情報を多数掲載しています。
運営会社:株式会社ビズアップ総研
公式HP:https://www.bmc-net.jp/