相続税専門の税理士の重要キーワード「相続税還付」について解説
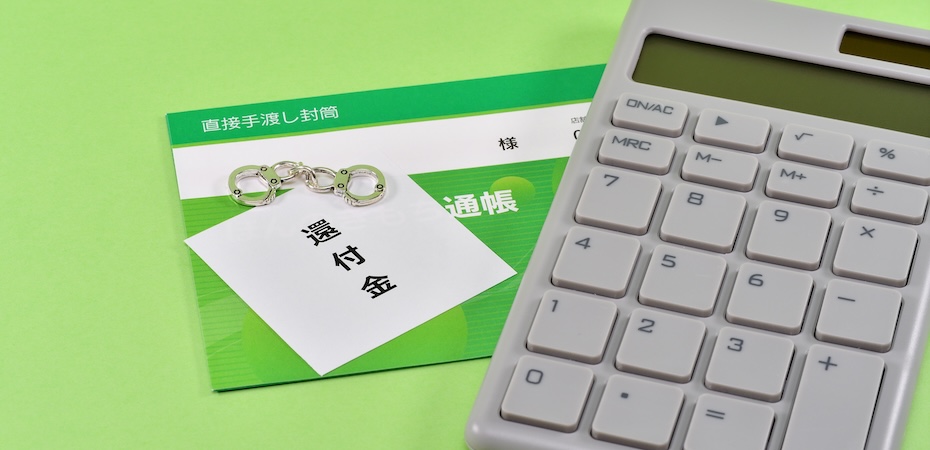
相続税は相続開始から10カ月以内の申告、納税が必要です。相続人の中には、遺産分割協議が長引くなどして、時間的な余裕がない中で慌てて申告、納税する人もいます。また、税理士も相続税の計算には慣れていないこともあります。そのため、相続税の納すぎとなり、相続税還付を受けられる状況にある方もいらっしゃいます。
相続税を専門的に手掛ける税理士なら、「相続税還付」は重要なキーワードになります。
目次
- 相続税が還付されることはあまり知られていない
- 相続税還付は、相続税専門の税理士にとって重要なキーワード
- 相続税が納めすぎになる原因
- クライアントに相続税還付を説明する場合:土地の相続税評価額に重点を置く
- 申告後に成立した遺産分割による相続税還付
- 相続税の更正の請求手続の注意点
- まとめ
相続税が還付されることはあまり知られていない

相続税に関して一般の人でもよく知っている事項は次のような事柄です。
- 相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人数)」で計算した額である。
- 相続税の申告、納税期限は、10ヶ月以内である(被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内)。
また、10ヶ月以内に申告、納税しなければ、延滞税が課されてしまうことも知られているでしょう。そのため、多額の遺産を相続した相続人は、その期限に向けて、相続税の計算や申告を急ぎがちです。
一方で、相続税の還付が受けられることは、あまり知られていません。
また、相続税還付のキーワードを見つけた人でも、国から相続税が納めすぎになっているという知らせが届いて還付されるというイメージを持っている方もいるかもしれません。
そもそも、相続税が納めすぎになることがあるのかと疑問を持つ方も少なくないでしょう。
相続税還付は、相続税専門の税理士にとって重要なキーワード
相続税を専門的に扱いたい税理士の方は、相続税の還付についても詳しく解説できるようにすべきです。
その理由を3つ紹介します。
相続税の申告納税を自分でやる人もいる
相続税の基礎控除額が下がった影響もあり、一般のサラリーマン家庭でも相続税を納税する人が増えています。しかし、相続税の額が少ない場合は、税理士に頼まず、自力で計算して納税してしまう方もいるかもしれません。
その場合、土地評価が適切にできていないために、相続税を納めすぎている可能性があります。そうした方に向けて、相続税還付の可能性について紹介するとよいでしょう。
相続税に詳しくない顧問税理士に依頼することもある
相続税が発生する人は、企業経営者も多いでしょう。経営者は税金の問題は、自社で抱えている顧問税理士に相談するのが一般的なので、相続税についてもその流れで、その税理士に相談したり、依頼する事が少なくありません。
しかし、企業の顧問税理士は、必ずしも相続税に詳しいとは限りません。
この場合、税理士と言えども、付け焼き刃の知識で相続税の計算を行ってしまい、結果として、相続税が納めすぎになっている可能性があります。
企業の顧問税理士は法人税や所得税には詳しくても、相続税に詳しいとは限りません。相続税のことは、相続税専門の税理士に相談すべきであることをアピールするとともに、相続税還付の可能性について紹介するとよいでしょう。
相続税の申告納税期限が10ヶ月以内
相続税は、申告、納税期限が10ヶ月以内ということもあり、直前になって慌てて申告、納税する方も少なくありません。
土地評価を高く計算していたり、控除の適用漏れがあることに気づかないままに申告、納税してしまい、結果として、相続税を払いすぎてしまうこともあります。
一方で、相続税還付を受けるための更正の請求は、法定申告期限から5年間なら可能です。
「相続税還付を受けられる可能性があるので、相続税の申告内容について落ち着いて検討してみませんか?」という形で案内するとよいでしょう。
相続税が納めすぎになる原因
相続税を納め過ぎてしまい、相続税還付が受けられる状況になる理由は、主に3つです。
相続税が自己申告納税制度のため
相続税は遺産を相続した相続人が自ら税額を計算して納税する自己申告納税制度となっています。
相続税を適切に納税するためには、次の課題をクリアしなければなりません。
- 法定相続人の数を確定する。
- 被相続人の遺産を調べる。
- 被相続人の遺産の価値を正確に把握する。
- 遺言書の有無の確認や遺産分割協議を行う。
いずれも厄介な課題で、専門家に依頼しても、時間がかかりますが、一般の方が自分でやろうとするとどこかでミスが生じることも少なくありません。
土地の相続税評価が難しい
被相続人の遺産に土地が含まれている場合は、土地の相続税評価額を適切に計算しなければなりません。相続税評価額が間違っていると、相続税を払いすぎたり、逆に少なすぎて、税務署から指摘を受ける原因になります。
ただ、土地の相続税評価額は、書類上の計算だけで簡単にできるわけではなく、土地の形状、立地条件、周辺の環境など、様々な要素を考慮する必要があります。
専門家でも経験や知識が足りないと、適切な計算ができないケースもあり、相続税を払いすぎてしまう原因になりやすいです。
相続税の控除の適用漏れがある
相続税では、様々な控除や特例が用意されており、これらを活用することにより、相続税の納税を免れたり、税額の軽減を図ることができます。
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減がよく知られていますが、他にも次のような控除制度があります。
- 未成年者の税額控除
- 障がい者の税額控除
- 外国税額控除
- 贈与税額控除
- 相次相続控除
これらの控除や特例があるのに、適用していない場合は、相続税額が増えたり、納税の必要がないのに気づいていないこともあります。
一般の方が自分で相続税の申告をしている場合はそうしたケースもあると考えられるので、控除の適用漏れがないか、チェックを促すとよいでしょう。
クライアントに相続税還付を説明する場合:土地の相続税評価額に重点を置く

相続税を納めすぎて、相続税還付になるのは、土地の相続税評価が適切にできていないことが原因となるケースが多いようです。
そのため、相続税還付の説明では、土地の相続税評価額の算定方法の解説に重点を置くとよいでしょう。まず、土地の相続税評価額は路線価方式で算出します。しかし、路線価で計算しただけで相続税評価額としてしまうと、高くなってしまい、相続税の納めすぎになります。
そこで、現地を確認するなどして個別的要因を考慮して、適切な評価を行う必要があります。また、土地に地上権などの権利が設定されている場合は、土地の評価額に影響してきます。
さらに、その土地が法令や条例、自治体の計画により、様々な規制の対象となっている場合も、評価額が違ってきます。
このあたりのことを説明して、土地の相続税評価額を見直しませんかという形で案内するとよいでしょう。
申告後に成立した遺産分割による相続税還付
相続税の申告と納税は10ヶ月以内に行わなければなりませんが、その間に遺産分割協議がまとまらなかった場合は、法定相続分で分割したものと仮定して申告、納税を行うことがあります。
その後、正式に遺産分割が成立した場合は、その内容によっては、様々な軽減や特例が適用されて、相続税が納めすぎとなるケースもあります。
このような場合も、相続税還付が受けられるので案内を忘れないようにしましょう。このあたりの話は、相続税還付よりも、「相続税の更正の請求」の話として紹介するとよいでしょう。
相続税の更正の請求手続の注意点
相続税還付を受けるためには、相続税の更正の請求手続きが必要です。
手続きの流れや申請書様式・記載要領については、国税庁のサイトで紹介されているので確認しましょう。
参考リンク:国税庁 相続税及び贈与税の更正の請求手続
相続税の更正は、法定申告期限から5年以内にしなければなりません。例外として、後発的理由などの特別な事情が発生した場合は、法定申告期限から5年を経過していても更正の請求が可能です。
この場合でも、その事実が生じた日の翌日から2か月又は4か月以内とされているので、期間に注意が必要です。国税通則法23条の説明になるため、詳しく紹介しましょう。
まとめ
相続税の納付は、一生に何度もあることはありませんので、年末調整や確定申告と異なり、慣れることはありません。そのため、税金に詳しい人でもミスが生じやすいですし、結果として、相続税を納めすぎになっているケースも少なくありません。
相続税専門の税理士の方は、相続税は還付を受けられる可能性が高い税金である旨を紹介し、専門性をアピールするとよいでしょう。
 オンライン研修・eラーニング
オンライン研修・eラーニング
e-JINZAIで
社員スキルUP!
- e-JINZAI for account(会計事務所向け)
- e-JINZAI for business(一般企業・団体向け)
- 今ならe-JINZAIを2週間無料でお試しいただけます!

税理士.ch 編集部
税理士チャンネルでは、業界のプロフェッショナルによる連載から
最新の税制まで、税理士・会計士のためのお役立ち情報を多数掲載しています。
運営会社:株式会社ビズアップ総研
公式HP:https://www.bmc-net.jp/






