公認会計士の仕事は激務?忙しい時期や、やりがいを感じる場面を紹介
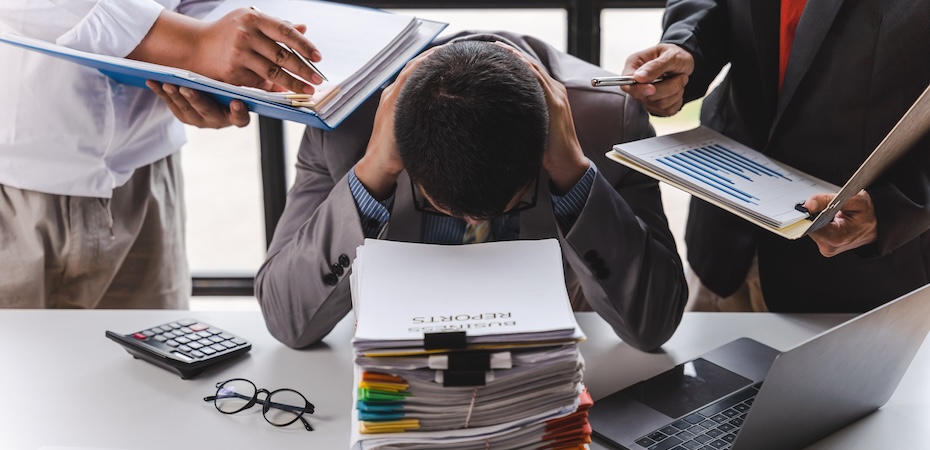
「公認会計士の仕事は激務と聞くけど、本当なのだろうか」「具体的には、どの時期に、どのくらい激務なのだろう?」と、悩んでいないでしょうか。
公認会計士の仕事は激務と言われていますが、職場や担当業務によって異なります。特に、大規模な上場企業を担当すると、激務になりやすいです。しかし、いつも激務なわけではなく、8月から10月の閑散期はゆとりのある働き方も可能です。
この記事では、公認会計士の仕事が激務と言われる理由について解説します。激務になる時期や、公認会計士になってよかったと感じるケースについても分かる内容になっています。
この記事を読み終える頃には、公認会計士の仕事に対する理解が深まり、自分自身のキャリアプランを描く上で、より具体的なイメージを持てるようになっているでしょう。
目次
公認会計士の仕事は激務なのか?

公認会計士は、企業の財務諸表が適正かどうかをチェックする専門家です。監査業務の他に、コンサルティングなど幅広い業務を担います。責任ある仕事である一方、激務というイメージを持たれがちです。
果たして本当に、公認会計士の仕事は激務なのでしょうか。ここでは、職場や担当業務、時期などの観点から、公認会計士の働き方について解説します。
職場や担当業務によって異なる
公認会計士の仕事内容は、勤める職場によって大きく変わります。監査法人に勤める場合、主な仕事は企業の財務諸表をチェックする監査業務です。一方、企業の経理部門で働く場合は主に財務諸表の作成などです。
一般的に、監査法人は繁忙期と閑散期があり、繁忙期には残業や休日出勤も珍しくありません。しかし、一般企業は比較的安定した業務量で、ワークライフバランスを保ちやすい傾向があります。
企業の経理部門で働く場合は、決算期など特定の時期に業務が集中しやすいです。一時的に忙しくなることはありますが、年間を通して見ると監査法人ほど激務ではないでしょう。
大規模な上場企業を担当する部署は激務になりやすい
大規模な上場企業は事業規模が大きく取引も複雑なため、チェックする書類の量も増えます。特に、決算期が集中する時期は、多くの企業の監査が重なり、残業が続くことも珍しくありません。徹夜で作業することもあり、体力的に厳しくなるでしょう。
しかし、このような激務を乗り越えることで、大きなやりがいを感じることができます。大規模な上場企業の監査は責任も重大ですが、得られる経験も大きく専門家としてのスキルアップにも繋がります。
8月から10月の閑散期はゆとりのある働き方ができる
8月から10月は閑散期と言われ、比較的ゆとりのある働き方ができます。この時期は残業も少なく、有給休暇を取得しやすいでしょう。資格取得のための勉強や、自己啓発のためのセミナーに参加するなど、自分のスキルアップに時間を使うことも可能です。
閑散期にも新規の監査案件が入ってくることもありますが、繁忙期と比べて業務量は少なく、比較的ゆとりのある働き方ができるでしょう。
公認会計士の仕事が激務と言われる理由
公認会計士の仕事が激務と言われる理由は、以下が挙げられます。
- 決算期が集中するから
- 高い正確性と専門性が求められるから
- 専門職のためすぐに人を増やせないから
ここでは、公認会計士の仕事が激務と言われる理由について解説します。
決算期が集中するから
3月決算を採用する企業が多く、担当する企業によっては決算業務が集中します。特に、上場企業を担当する場合は、忙しさが増すでしょう。
高い正確性と専門性が求められるから
会計基準や税法などの専門知識を常にアップデートし、高いレベルの専門性を維持する必要があります。監査業務では、企業の財務諸表に誤りや不正がないかを厳しくチェックする必要があり、わずかなミスも見逃せません。常に緊張感を持ちながら業務に取り組む必要があり、精神的な負担も大きくなります。
例えば、監査業務では、企業の会計処理が適切に行われているか、会計基準に準拠しているかを一つ一つ確認する必要があります。また、企業の内部統制が有効に機能しているか、不正リスクがないかなどの評価も必要でしょう。
専門職のためすぐに人を増やせないから
公認会計士は、国家資格であり専門性の高い職業です。業務量が増えてもすぐに人を増やして対応することはできません。資格取得には厳しい試験を突破する必要があり、合格率も低いため人材の確保が難しい現状です。
また、資格取得後も実務経験を積みながら専門性を高めていく必要があり、一人前の公認会計士になるには多くの時間と努力が必要です。
決算期に業務量が急増した場合でも、すぐに新しい公認会計士を採用して対応することは難しいでしょう。たとえ採用できたとしても実務経験が浅い場合は、先輩社員が指導しながら業務を進める必要があり、効率が悪くなってしまうこともあります。
既存の公認会計士が限られた人員で業務をこなさなければならず、長時間労働や休日出勤を余儀なくされることも少なくありません。
公認会計士の仕事が特に激務になる時期
公認会計士の仕事は一年を通して重要な役割を果たしていますが、特に仕事量が大幅に増加し激務となる時期があります。具体的には、以下が挙げられます。
- 4月中旬から6月上旬
- 四半期決算の前後1ヶ月
ここでは、公認会計士が特に激務になる時期について解説します。
4月中旬から6月上旬
この時期は、3月期の決算業務が集中するため、公認会計士にとって最も忙しい時期と言えるでしょう。企業は、決算短信や有価証券報告書などの財務諸表を作成し、株主総会に向けての準備を進める必要があります。
公認会計士は、これらの財務諸表が適正であるかどうかを監査し、監査報告書を作成する必要があります。
四半期決算の前後1ヶ月
上場企業は、3ヶ月ごとに四半期決算を行い、公表する義務があります。四半期ごとの監査は、決算監査ほど大変ではありませんが、企業の財務状況を正確に把握し、監査報告書を作成するためには、多くの時間と労力を要します。
特に近年は、企業を取り巻く環境が急速に変化しており、四半期ごとの業績変動も大きくなっています。公認会計士は、最新の会計基準や法規制を常に把握し、適切な監査手続きを実施しなければなりません。また、企業の経営陣との緊密な連携も重要であり、会計処理に関する疑問点や懸念事項を迅速に解決していく必要があります。
公認会計士になってよかったと感じるケース

公認会計士は激務と言われていますが、大きなやりがいを感じられるケースもあります。ここでは、公認会計士になってよかったと感じるケースについて解説します。
ケース1:高収入を得られるとき
公認会計士は、他の職業と比べて高収入を得やすいです。特に、経験を積んで大手監査法人やコンサルティングファームで活躍するようになれば、年収1,000万円を超えることも珍しくありません。
例えば、大手監査法人でマネージャーとして働く公認会計士の場合、年収は1,200万円程度になることもあります。高収入を得ることで、経済的な安定はもちろん、趣味や旅行など、プライベートも充実できます。また、家族がいる場合は、安心して養っていくことができるでしょう。
ケース2:海外で活躍できるとき
グローバル化が進む現代において、公認会計士は海外で活躍できるチャンスも豊富にあります。会計基準や監査基準が国際的に統一されつつあり、公認会計士の知識が必要とされているとも言えます。
例えば、海外企業の日本法人での勤務や海外の監査法人への転職などです。また、国際的なプロジェクトに参画し、海外の専門家と協力して業務を行うこともあるでしょう。
ケース3:独立開業するとき
公認会計士は、独立開業しやすい資格の一つです。自分のペースで仕事を進めたい、自分の能力を最大限に活かしたいと考えている人にとって、独立開業は大きな魅力となります。
例えば、会計事務所を開業して、企業の会計や税務をサポートできます。また、コンサルティング業務やセミナー講師など、自分の得意分野を活かした活動も可能です。
独立開業すれば、仕事の自由度が高まり、やりがいも大きくなります。成功すれば、大きな収入を得ることも可能です。公認会計士は、自分の力で道を切り開きたいと考えている人にとって、非常に魅力的な職業と言えるでしょう。
公認会計士は激務に関するまとめ
公認会計士は、企業の財務諸表を監査し、その正確性を保証する専門家です。監査業務の専門性が高く、正確性が求められることから、多くの責任を負うことになります。また、3月決算の企業が多いため、決算期には業務が集中し、長時間労働や休日出勤を余儀なくされることも少なくありません。さらに、人材の確保が難しいことも、激務の一因となっています。
しかし、公認会計士は高収入を得られる可能性が高く、経済的な安定を得やすいというメリットもあります。また、国際的な活躍の場も多く、海外企業や海外の監査法人で働くことも可能です。さらに、独立開業して自分のペースで働くこともできます。
公認会計士は激務ではありますが、それに見合うだけのやりがいと魅力のある職業と言えるでしょう。
 オンライン研修・eラーニング
オンライン研修・eラーニング
e-JINZAIで
社員スキルUP!
- e-JINZAI for account(会計事務所向け)
- e-JINZAI for business(一般企業・団体向け)
- 今ならe-JINZAIを2週間無料でお試しいただけます!

税理士.ch 編集部
税理士チャンネルでは、業界のプロフェッショナルによる連載から
最新の税制まで、税理士・会計士のためのお役立ち情報を多数掲載しています。
運営会社:株式会社ビズアップ総研
公式HP:https://www.bmc-net.jp/
































