激変期の会計事務所を支える「心の強さ」
レジリエンスが生産性を高め、離職を防ぐ

現代のビジネス環境は、かつてないスピードで変化を続けています。特に専門性の高い会計事務所では、テクノロジーの進化や顧客ニーズの多様化により、従来にはなかったストレスや負荷に直面する場面が増えています。
本記事では、そうした環境に適応する力として注目されるレジリエンス研修の重要性とその効果について、エンゲージメントを高める職場風土づくりの専門家である中村英泰先生にお話を伺いました。
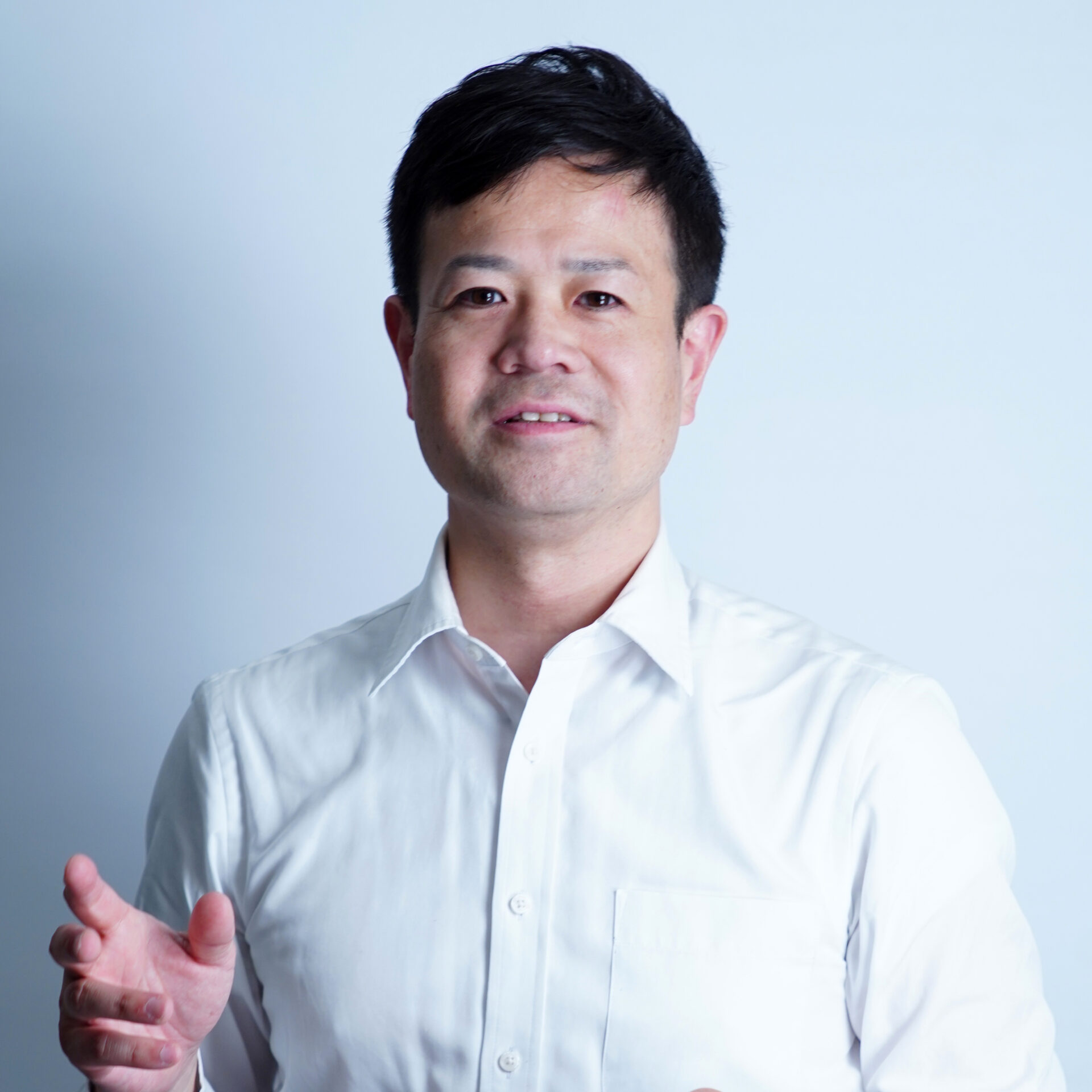
中村 英泰
株式会社職場風土づくり/代表取締役 人材サービス業界で15年 働くなか、企業規模に関係なく「社員が働き続ける“いい職場”」が存在することに気付く。2014年に「職場風土づくり」を目的に起業。現在、研修や講演、中小企業の職場風土づくりの支援活動を通じたワークエンゲージメント向上に取り組んでいる。著書に「社員がやる気をなくす瞬間 ~間違いだらけの職場づくり」がある。
― はじめに、レジリエンスとは何か、また、ビジネスでレジリエンスが必要とされる背景について教えてください。
レジリエンスとは、逆境や困難、強いストレスに直面した際に、“心のバランスを保ちつつ、状況に適応しながら物事を進展させていく力”のことです。近年のビジネス環境は、AIなどのテクノロジーの発展による急速な変化への適応や、VUCAが示すような正解のない課題に取り組まねばならない場面が増えています。そうした状況下において、持てる能力を活用しパフォーマンスを発揮するために、レジリエンスの重要性が一層高まっています。
― とくに会計事務所の仕事にレジリエンスが必要な理由を教えてください。
会計事務所の現場でも、レジリエンスの重要性は増しています。例えば、ICTやAI、OCRの精度向上などのテクノロジーを活用し、業務の進め方や取り組み方を変化させることが求められるようになっています。こうした変化にうまく適応できず、ストレスを感じる職員が増えています。
また、リモートワークなど新しい働き方の広がりにより、これまで同僚との雑談や愚痴で自然に解消されていた仕事のストレスが、発散しにくくなっています。その結果、ストレスへの対処が個人に委ねられる場面が増えています。
さらに、今後一層、顧客の期待の多様化が見込まれます。その中で、職員が変化やプレッシャーに柔軟に適応できることが、会計事務所としての付加価値となっていくことを考えると、レジリエンスは職員にとっても、会計事務所にとっても欠かせない力といえます。
― レジリエンスが低いと、職場でどのような課題が起こりうるのでしょうか。
職員のレジリエンスが十分でないと、職場には次の三つの課題が生じることが考えられます。
まず一つ目は、仕事への意欲が低下することです。「今以上の業務に取り組もう」という気持ちが薄れると、自信を失い、ミスを恐れて消極的になってしまいます。
こうした状態は、動機づけ低下症候群(※1)としても知られています。このような状況に陥ると、本人の成長が止まるだけでなく、職場全体の士気にも悪影響を及ぼします。
二つ目は、メンタル不調を発症することによる突発的な休職や離職です。強いストレスを抱え続けることによって、ある日突然、心が折れて働けなくなってしまうことがあります。それにともない、急な業務の引き継ぎやチームの再編成が発生するなど、多くの職員が想定外の負荷への対応を求められることになります。
最後に、定着率の低下です。働くことによるストレスは、どんな組織でも、どんな職業に就いていても必ず発生するものです。むしろ、目の前のストレスを調整して乗り越えることで、次の挑戦が可能になります。
レジリエンス力が低いと、ストレスを避けるために安易な退職を選択してしまいます。現代は人材確保が難しく、採用・育成にかかるコストは高くつきます。加えて、抜けた穴を埋めるための周囲の負担も無視できません。
このように、レジリエンスの不足は、個人の問題にとどまらず、組織全体の持続性に大きな影響を及ぼします。
※1 動機づけ低下症候群とは、ストレス状態が続くことで気力や興味・関心が著しく低下し、積極的な行動ができなくなる状態(うつ状態ではない)。
― レジリエンス研修は、特にどの階層の職員に効果的でしょうか。
職員のレジリエンス力を高めるには、レジリエンス研修が最も効果的です。対象として、すべての階層の受講が望ましいです。新人だから不要、中堅だから関係ない、管理職は自力で対処すべき、といった線引きはできません。
とはいえ、特に重要なのは中間管理職です。管理職には、自身のセルフケアに加え、部下への支援・フォローの役割が求められます。さらに組織全体の生産性を高めるうえでも、管理職のレジリエンス向上は大きな鍵です。自身のパフォーマンス向上と同時に、チーム全体への好影響も期待できます。
― レジリエンス研修は、どのような内容を扱うのでしょうか。
研修では始めに、レジリエンスを高めることの目的と考え方を学びます。レジリエンスとは何か、なぜ今の時代に求められているのかを知り、もともと持っている力をどう目覚めさせるかの視点を持ってもらうのです。
次に、自分の状態を知るためにセルフチェックをします。過去にうまくいかなかった経験を振り返り、それがストレスと関係していた可能性を考えることで、自身のストレス耐性や傾向を自覚してもらいます。
最後は、学んだことを行動に結びつける実践です。レジリエンスは知識ではなく、実践にしてこそ効果を発揮するため、例えば「仕事の負担が増し、強いストレスを感じたときにどのように乗り越えるのか」のように、階層ごとに設定されたケースに取り組みながら、明日から何を変えるか、自分にとってどのような工夫が必要かを考えてもらいます。
― レジリエンス研修で身につくスキルには、どのようなものがありますか。
研修では、「しなやかに折れずに困難を乗り越える力」「ストレスと適切に向き合うことが、人を成長させるという認識」が養われます。加えて、チームのメンバーが、“自らの自信を支える3つの感覚-自分が役に立っていると実感できる「自己有用性」、自らの行動が結果につながると信じられる「自己原因性」、そして自分自身を肯定できる「自己肯定感」を育むこと”の重要性を再確認することが期待できます。これらは、自律的なチームづくりには不可欠な要素でもあります。
これによって、職員個々に“自分だけでなくメンバーが困難を乗り越えることで、チームの成果をより向上させられるかもしれない”という意識が育ち、メンバーへの共感や協力の意識を向上させることや、チームビルディング、さらには心理的安全性の向上にもつながります。
― 研修を通じて、チームや職場にはどのような変化が期待できますか。
レジリエンス研修を実施することで、先述した三つの課題が反転し、「離職率の低下」「生産性の向上」「しなやかで強い組織づくり」を可能にすることが期待できます。さらに、多くの組織で損なわれつつあることが指摘されているエンゲージメントの向上も大いに期待できます。
― 最後に、レジリエンス研修の実施を検討している会計事務所に一言メッセージをお願いします。
ITやAIの進化により、会計事務所の業務が変化するとともに、顧客は正確な実務対応に加え、付加価値のある提案や柔軟な対応を期待するようになってきています。これらの力は、職員一人ひとりの精神的な安定や自信とも深く関わっています。
変化に適応し、職員が力を発揮できる環境をつくるために、レジリエンス研修は非常に有効です。働きやすさややりがいの醸成にもつながり、組織として人を大切にしているという職員へのメッセージにもなります。
心の不調は外からは見えにくく、放置すると、優秀な職員を失うだけではなくチームが崩壊する可能性もあります。レジリエンスは、変化の時代を前向きに生き抜くための土台です。今後の組織づくりの一環として、ぜひ導入を検討してみてください。
































