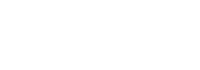合同会社からの利益の配当<深読み 最新税制レビューVol.6>

佐藤信祐事務所 所長 公認会計士・税理士 博士(法学)
佐藤 信祐 先生
2023/6/26
業界屈指の専門家である佐藤信祐先生が、さまざまな税制や組織再編等に関する新しい論点・最新情報、少しマニアックな税務トピック、判例裁決事例など、独自の視点で解説します。
合同会社では、それぞれの社員に対して損益分配により利益の額が分配されることになる(会社法622)。すなわち、株式会社と異なり、貸借対照表に計上されている利益剰余金の額は、どの社員の利益剰余金の額なのかが明確にされているといえる。
それでは、利益の配当をどのように行うのかというと、会社法621条1項において、「社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。」と規定されていることから、社員の請求により利益の配当が行われることになる。
そうなると、損益分配の時点で課税されるのか、利益の配当を請求した時点で課税されるのかが疑問になる。この点につき、所得税基本通達36-4及び法人税基本通達2-1-27(1)ロでは、会社法621条2項に基づく定款で定めた日がある場合には定款で定めた日、定款で定めた日がない場合には、社員総会の決議があった日に利益の配当の効力が生じることが明らかにされている。さらに、髙橋正朗『法人税基本通達逐条解説』207頁(税務研究会出版局、十訂版、令和3年)では、「当該利益の配当又は剰余金の分配に関する決議のあった日に具体的な配当金支払請求権が成立すると考えられることから、当該決議のあった日がその収益計上時期となる。」と解説されている。
ただし、実務上、利益の配当の効力発生日を社員総会の決議により定めていることは稀ではなかろうか。さらに問題となるのは、定款の定めがない場合には、「持分会社は各事業年度に係る計算書類を作成しなければならないから(617②)、定款の定めがないときは、利益配当は事業年度の終わりに定期的に実行されることになる(青竹正「利益の配当」奥島孝康ほか編『新基本法コンメンタール会社法3』51頁(日本評論社、平成21年))。」という解説があることから、決算が確定した段階で配当金支払請求権が生じ、社員で課税関係が生じるという解釈も成り立ってしまうという点である。
この点については、前述の通達の文言から、利益の配当に係る社員の合意があるまでは、社員で課税関係を生じさせていないことが一般的であると思われる。さらに、会社法上も、社員が利益の配当を請求した時点で配当金支払請求権が成立するという考え方もある(大杉謙一発言「座談会 合同会社等の実態と課題(下)」商事法務1945号34頁(2011年))。
このように、定款に定めがない場合の取扱いについては、必ずしも明確とはいい難いことから、実務上、定款で定めておくことが望ましいと考えられる。