士業の未来を拓くRPA活用術とは
士業RPA BizRobo! 協会が変革する税理士業務の課題と可能性

(一社)CPA 士業RPA BizRobo! 協会 代表理事/税理士法人オールシエンシア 代表社員 税理士 佐久間 隆
株式会社MACコンサルタンツ MACミッドランド税理士法人 東京日本橋支店 副支店長/AI&DXソリューションラボ エグゼクティブディレクター 山田 洋和
BizRobo! 導入で士業の働き方改革を推進
まず、佐久間先生の税理士事務所でRPAを導入されたきっかけと背景について教えてください。
佐久間先生(以下佐久間):一番のきっかけは、確定申告時期の長時間労働でした。繁忙期はどうしても業務が集中し、効率化が急務だったのです。6年ほど前、勉強会でRPAというITツールを知り、「これは使える」と思って検討を始めました。RPAは、ルーティン業務や定型作業の自動化にとても適していて、まさに当時の課題解決にぴったりでした。まず取り組んだのは、異なる会計・税務システム間のデータ連携。手入力で対応していた決算情報の移行をロボット化しました。ひとつのロボットに指示を詰め込みすぎると動作が重くなるので、用途ごとにロボットを分けていく方針で進めましたね。

こういった経験を基に、士業におけるRPA推進のノウハウやロボットの共有を目的に設立したのが、一般社団法人CPA 士業RPA BizRobo! 協会です。
数あるRPAツールの中で、BizRobo! を選定された理由は何でしょうか。
佐久間:当時、事務所で使っていたメインシステムが他のRPAではうまく動かないという話を耳にしていました。でも、BizRobo! にはトライアル期間があり、実際に試したところ問題なく動作したのです。それが決め手になりました。
山田氏(以下山田):実は弊社でも、佐久間先生の事務所と同じシステムを使っていたんです。以前使っていたRPAでは不具合が多く、BizRobo! が問題なく動作すると聞いてとても魅力を感じました。
佐久間:BizRobo! は「画像認証」と「オブジェクト認証」の両方に対応しているのも強みです。画像認証だけだと、アイコンの位置や色が少し変わるだけで認識しなくなる。でもオブジェクト認証なら、構造そのものを読み取ってくれるので、多少のシステム改修があっても継続使用ができるんです。
山田:パソコンの画面の縮尺が違うだけで動かなくなるツールもある中で、BizRobo! はそうした問題が起きにくい。そこも安心して導入できた理由のひとつですね。
RPAとAIの違いについて、先生方はどのように認識されていますか。
佐久間:RPAは定型業務を繰り返し処理する、いわば作業ロボット。判断はせず、決められたことを正確に実行する仕組みです。一方、AIは判断や推論が可能で、構造そのものがRPAとは異なります。
山田:まさにその通りで、私は「AI=考える頭脳」「RPA=動く手足」と捉えています。まずは私たちがAIに「こんなことをやりたい」と指示し、AIが「これをやって」と考えて、RPAがそれを実行する。今後はそうした連携が進むと思います。
佐久間:組み合わせたハイブリッド運用も現実になるでしょう。今は別々に使うケースが多いですが、融合すれば、たとえばチャットボット的な活用も可能になりますね。
山田:私は、生成AIに「こういうロボットを作って」と頼める未来を期待しています。さらに、kintoneとの連携で新規顧客の情報をAIが抽出し、それをRPAが自動登録するような仕組みができたら理想的です。RPAの市場も伸びていますし、今後の可能性はまだまだ広がっていると感じています。
協会のサポート体制が後押しする
付加価値創出型の BizRobo! 導入効果と優位性
BizRobo! は会計・税務システムとの親和性も高いとのことですが、対応状況はいかがでしょうか。
佐久間:多様なシステムを使っていますが、BizRobo! と相性が悪かったケースは聞きません。幅広い税務会計ツールに対応可能だと感じています。ただし実際にロボットを作るには、多少のプログラミング的な理解が必要なので、初めて触る方には少し難しく感じるかもしれません。
山田:私も初めて画面を見た時に、どこから手を付けていいのか戸惑った記憶があります。そこも含めて佐久間先生にサポートしていただいたので、大変助かりました。
佐久間:ライセンス面の利点としては、BizRobo! は1ライセンスで複数のロボットを稼働できることが挙げられます。他社のRPAではロボット数を増やすごとに従量課金となるケースもあると耳にしますので、コスト面でも優位です。また、BizRobo! は自社でも開発・修正ができる柔軟性があり、開発リソースがない場合は当協会で支援することも可能です。
山田:弊社でも、当初は他のRPAを自社開発で進めていたのですが、みんな本業と両立するのが困難で、なかなか時間の確保もできないし、良いアイデアも出てきづらかったようです。その中で佐久間先生と協力させていただくことで、協会が持つ100以上のロボットリストから選んで導入できたことに大きなメリットを感じました。画面変更などのメンテナンス対応もしっかりしていて、安心して運用できています。
BizRobo! 導入後、MACコンサルタンツにおける業務プロセスにどのような変化がありましたか。
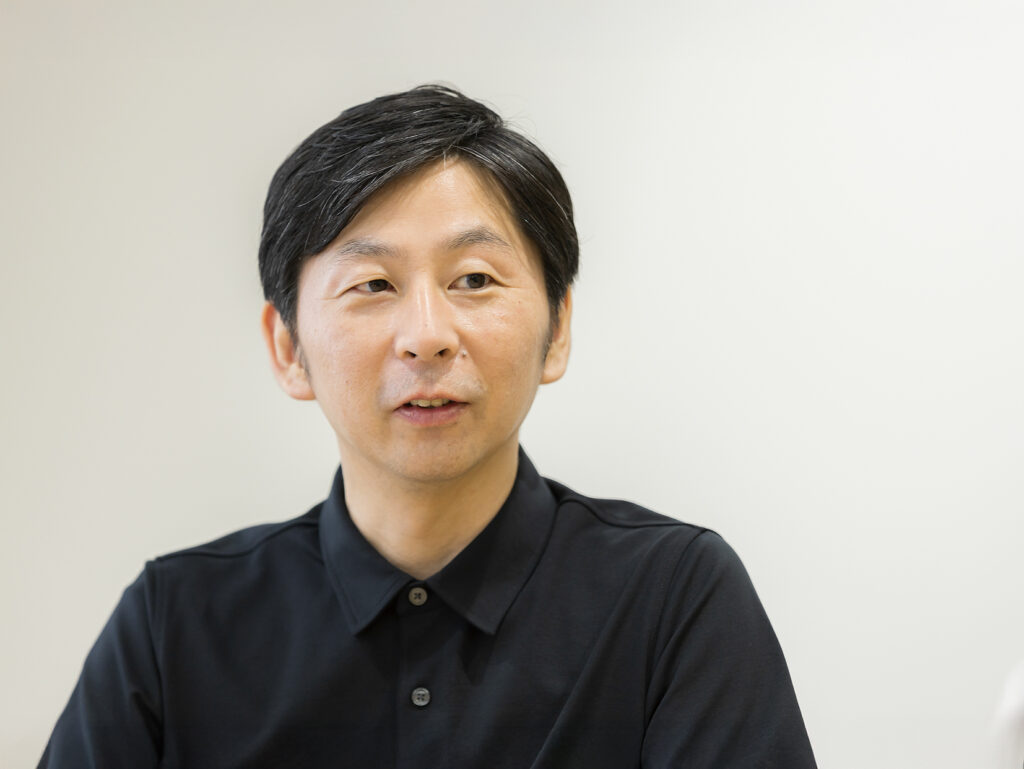
山田:業務の進め方が大きく変わりましたね。まずは、ひとりの担当者任せだった一連の業務を工程ごとに切り分けて分業体制を確立。そのうえで、区分けした工程の中でも、特に自動化が可能である定型的な申告書の出力やデータ転記などでRPAを活用した結果、待ち時間が大幅に短縮され、「作業が格段に楽になった」という声が多く上がっています。人手不足のなかで、RPAによる効率化は担当者の処理量アップにつながり、売上の拡大や実質的な人員増にもつながると感じています。
佐久間:幸いなことに、RPAの導入に際して反対意見というのは今まであまり聞かなかったのですが、「仕事が奪われるのでは」と不安に感じる方の気持ちも理解できます。税理士業界には職人気質の方も多く、従来のやり方にこだわる傾向があるのも事実です。
ただ、物価は上がっても報酬単価はなかなか上げにくい。その中で利益を確保するには、自動化・効率化が必要不可欠です。ルーティン作業はロボットに任せ、人間は付加価値の高い業務に集中する。それが従業員にも会社にも顧問先にもプラスになります。これからはRPAやAIを「使う側」に立てるかが重要になるので、自分の仕事の幅を広げていくチャンスとして、RPA導入を前向きに捉えてもらえると嬉しいです。
MACコンサルタンツではBizRobo! 導入以前から
別のRPAシステムを導入されていたとのことですが、
業界内でも早期からRPAに取り組んでいらっしゃったのですね。
佐久間:私が初めてご一緒したのは5年ほど前ですが、その時点ですでに2年ほど前からRPAを導入されていたと記憶しています。非常に感度の高い、先進的な事務所だと感じました。
山田:特に弊社の会長がAIやRPAに強い関心を持っていて、導入をリードしていました。弊社には、社員、アルバイト、パートなど全従業員が所属する委員会組織があるのですが、現在私が所属する「ラボ」は、RPAを専門に取り組む「RPA委員会」の活動を吸収・進化する形で生まれた組織です。ラボでは、RPA委員会時代を含め、営業や採用といった各委員会からあげられた幅広い社内の課題に対して、どんなロボットが作れるかを議論しています。そして「こんなことが自動化できたら便利」といった声をもとに、佐久間先生に相談し、実現の可能性を検討し、導入を支援していただいています。私たちとしては「こんなことできますか?」と言うだけで、佐久間先生側がそれを実現してくださるので、本当にありがたく思っています。
佐久間:要望を言っていただけるのが、正直とてもうれしいです。一番残念なのは、せっかく支援してRPAを使ってもらったにもかかわらず、成果も可能性も感じられないままやめられてしまうことなので。もちろん難しい要望もありますが、他事務所の課題解決のヒントにもなるので、積極的に発信してもらいたいです。
今は、導入事務所でも積極的に要望を伝えてくれるケースはまだ少なく、多くは「今のままで十分」と感じている印象です。もっと使いこなしたい、その先に何ができるかまで考えている事務所の割合は少ないと感じます。だからこそ、こちらからも「どんどんリクエストください」と働きかける必要があります。定期的なアプローチで、眠っているニーズを掘り起こしていきたいと考えています。
RPA導入成功の鍵は
事務所規模に応じたサポートと「共有」
RPAはどのような事務所で特に効果を発揮するとお考えですか。
佐久間:やはり、規模が大きい事務所ほど効果は出やすいです。件数の多い定型業務を自動化することで、効率化のインパクトが大きくなりますから。とはいえ、小規模事務所からのニーズも多く、より幅広い導入を目指して、メーカーと連携し、5名以下・10名以下といった規模別の新プランを開発しました。
特にBizRobo! は、データ連携はもちろん、データの出力やアウトプット業務にも非常に適しているので、公文書のダウンロードや、電子申告後の税務帳票の出力など、提出した書類を社内サーバーやクラウドシステムに保存するロボットは非常に効果が高いです。これらは規模にかかわらず、全ての税理士事務所で活用できる汎用性の高い自動化対象業務なので、今後さらに普及が進むことを期待しています。
RPAを導入する際、事務所の規模によって異なる課題や着眼点があると思いますが、
それぞれにおいて重要だと感じる視点を教えてください。
山田:大規模な組織では、各部署から多様なRPA活用アイデアが出る反面、部門間の「縦割り」がネックになることがあります。たとえば同じ申告書の出力でも、部署ごとに保存場所が違うなど非効率が生じがちです。今後は「縦ではなく横につなぐ」意識が大切だと感じています。
佐久間:一方、小規模事務所では所長先生がおひとりで多くの業務を担っているケースが多く、RPAを使えばその負担を軽減し、業務の質を高めることが可能です。ただ、開発や運用に時間を割くのは物理的に難しいので、そうした事務所が本業に集中できるよう、自動化を支援する体制を今以上に整えていきたいと考えています。
山田:多くのロボットを持つ協会のような存在があると、他の事務所はその中から自分の事務所に合ったものを選んで使うことができます。共通の悩みを共有し、同じシステムを使う仲間同士でノウハウを生かしていくことで、業界全体が効率化し、発展していければと思います。
実際の現場では、RPAの導入・定着がうまく進まないケースもあるかと思いますが、
どのような壁や課題が多いと感じられますか。
佐久間:一番多いのは、「社内で対応したほうが安い」といった経営判断です。また、導入しても思ったより活用範囲が狭かったり、今のやり方を変えたくないという理由で定着しなかったりというケースもあります。最初の面談でも感じるのが、「難しい業務」から自動化しようとして開発が大変になり、続かなくなること。まずは単純で量が多い業務を自動化し、そこで空いた時間を使って次の開発へ ― このステップを踏むことで、RPAの効果を実感しやすくなると思います。
税理士業界のこれからとRPAへの期待
税理士に求められる役割が広がる中で、専門性や最新情報のキャッチアップに加え、
業務効率化も重要なテーマになってきています。そうした多様なニーズに対応する上で、
RPAをどのように活用していくべきだとお考えでしょうか。
佐久間:今税理士に求められているのは、相続、事業承継、M&A、経理代行、保険の提案・プランニング、補助金や助成金の活用、AIの導入支援やコンサル、業務効率化の支援など多様な専門性と最新情報のキャッチアップです。要望が多岐に渡るということは、良い意味で捉えると、税理士業務の可能性の大きさを示しているとも言えますね。ただし、こういったクライアントのさまざまなニーズに応えるためには、やはり時間の捻出が不可欠です。その時間を生み出すために、ルーティン業務のRPAによる自動化は非常に重要だと考えています。
山田:RPAは「作業の自動化」のイメージが強いですが、将来的には知的判断を伴う業務にも活用されていくことを期待しています。先ほどのAIとの連携の話にもつながりますが、誰もが自分の業務を簡単に自動化できる、そんな環境が理想です。
佐久間:士業、とくに税理士業界は、もっと魅力的に感じてもらえる仕事だと私は考えています。これだけ専門的な知識でクライアントを支えられる職種は、他にはなかなかありません。でも、現場ではルーティン業務に追われて、その魅力が伝わりきっていない部分もある。だからこそ、業務効率化できる部分は、RPAを使って生産性を高めれば、より高度なサポートが提供できるようになるし、スタッフの待遇や働きがいも向上していくはずなのです。そうした好循環が生まれれば、業界全体の魅力も自然と高まっていくと考えています。
今後、RPAやDXの進化が加速する中で、必要だと感じることがあれば教えてください。
山田:生成AIの進化を見てもそうですが、今後はRPAも他のツールと統合されて、より直感的に、誰でも使えるようになっていくと思います。生成AIは、最初はただ質問に答えるだけだったのが、今では議事録も作成できるようになっていますよね。RPAも同じで、将来的には「作らなくても使える」方向に進化していくのではないでしょうか。現状では各事務所がそれぞれ個別にRPAの仕組みを構築しているのが現実です。もしこれが、業界全体で共通して使えるものがあれば、個別開発にかかる手間が省けて、本来注力すべき対顧客業務にもっとリソースを割けるようになるのではないかなと期待しています。国民性なのか、日本では「自社にぴったり合うもの」を求めがちだと感じるのですが、それがDXを遅らせる要因になることもあります。実際には、ある程度パッケージ化されたものをベースに業務を合わせたほうが、乗り換えも運用もスムーズではないのかなと思います。
佐久間:kintoneもそうですよね。ノーコードで自由に作れるのは強みですが、あまりにカスタマイズしすぎると自社専用の仕様になってしまって、逆に汎用性を失ってしまう。一方、RPAは業務を標準化することで、そうした「終わりのない独自化」から抜け出せる可能性があると思います。
山田:たとえば会計ソフトのように市販の標準仕様があると、RPAの導入もずっとラクになりますよね。無限に作り込もうとせずに、ある程度の割り切りがあっても良いと思うのです。
佐久間:ニーズに応えようとすれば、どこまでも自動化できてしまいます。でも、それを全部やろうとすると、逆に手間ばかりかかってしまう。だから「100%自動化」は目指さず、できる範囲で効率化・標準化しながら業務と並走する。そのバランス感覚が、今後は大事になってくると思います。
| プロフィール |
|---|
|
































