プロジェクト型案件を受注する
<税理士がコンサルタントとして活躍するためには?⑤>

日沖コンサルティング事務所・代表
中小企業診断士、中小企業大学校・講師、産業能率大学・講師
日沖 健
6回に渡って税理士がコンサルタントとして活躍するためのポイントをお伝えするシリーズの5回目。今回は、プロジェクト型コンサルティング案件の受注と進め方のポイントを見ていきましょう。
プロジェクト型コンサルティングのニーズが拡大している
近年、プロジェクト型コンサルティングのニーズが広がっています。プロジェクト型コンサルティングとは、クライアントのメンバーとコンサルタントがプロジェクトを編成し、長期間かけて問題解決を進めるというコンサルティングです。
税理士の既存業務に近いところで、以下のような有望分野があります。
- 経営理念・パーパスの策定
- 中期経営計画策定
- 新事業開発
- 事業承継
- M&A
たとえば、事業承継というと、従来は「相続税をいかに節税するか」が経営者の唯一無二の課題でした。ところが、後継者難からM&Aを志向する経営者が増えています。また、事業承継を期に経営理念を見直したい、新規事業に取り組みたい、というニーズもあります。
税理士は、日ごろからクライアントの税務相談に乗っていることから、こうしたニーズに対応しやすいでしょう。
ただし、経営相談(第3回)やアウトソーシング型業務(第4回)と比べて、プロジェクト型コンサルティングは受注面でも受注後の実行面でも難易度が格段に高まります。
コンサルティングをいきなり提案しても
プロジェクト型コンサルティングで最も難しいのは、やはり受注です。
税理士は、コンサルティング受注において最も重要なクライアントからの信頼をすでに獲得していますし、経営者と普段着のコミュニケーションができます。税理士は、この圧倒的に有利な立場を生かして、コンサルティングを提案することができます。
といっても、いきなりコンサルティングの提案をしたら、経営者は引いてしまいます
社長、今日は折り入ってご提案したいことがあります
え、何ですか。改まって
御社の長期的な発展のために、パーパス策定のコンサルティングをしませんか?
パーパス? 何ですか、それ?
経営理念に近いのですが、会社が存在する目的のようなものです。御社には先代社長が打ち出した“創業の精神”はありますが、経営理念はありませんよね
ええ、ありませんが
しっかりしたパーパス、つまり会社としての旗印を作って、その実現に向けて全社一丸となって取り組むようにするべきです
経営理念について、まったく考えていなかったわけではありませんが…。で、コンサルティングというのは?
従業員からメンバーを選んでプロジェクトを編成し、私のアドバイスを得ながら経営理念を策定するというやり方をご提案したいと思います
なんだか、大掛かりですね
大事な経営理念です。それくらいの体制でやらないといけません
そうですか。お話は承りました。まあ、他にも色々と喫緊の課題があるので、おいおい考えることにしたいと思います
この経営者が、この税理士にコンサルティングを依頼することはないでしょう。
経営診断をまず提案しよう
税理士は、いきなりコンサルティングを提案するのではなく、経営診断の実施を提案すると良いでしょう。経営診断とは、クライアントの経営状態を包括的に調べて、経営に問題がないか明らかにすることです。言うなれば、企業の健康診断です。
経営者は、必ずしも自社の問題をしっかり整理できているわけではありません。問題点がはっきりしない場合や他にも問題がありそうだという場合、経営診断の実施を提案します。
いきなりコンサルティングを提案されたら引いてしまう経営者も、経営診断で自社の問題点を分析するということには抵抗が少ないでしょう。
経営診断の留意点
経営診断を実施する上で留意したいのは、総合診断を行うことです。
経営者もコンサルタントも、会社の問題点について色々と考えていますが、その認識が正しいとは限りません。経営診断では、問題だと思ったことだけでなく、経営の色々な側面を総合的に調べます。
たとえば、経営者が「営業担当者の商品説明に問題がある」と考えていたとしても、
- 営業だけでなく、調達・設計・製造・経理・総務などあらゆる経営機能を調べます。
- 営業担当者という人材だけでなく、資金・設備・情報などあらゆる経営資源を調べます。
- 商品説明というオペレーションだけでなく、上位概念である戦略についても調べます。
- 戦略だけでなく、組織についても調べます。
プロジェクトで成果を実現する
経営診断によって対処するべき問題が明確になったら、コンサルティングの実施概要をまとめたプロポーザル(提案書)を作って、経営者に提案します。そして、契約し、プロジェクトを始めます。
ここでは、プロジェクト運営の留意点を3つ紹介します。
留意点① 重要課題に焦点を当てる
中小企業は、たいてい問題だらけです。コンサルタントもクライアントも、せっかくコンサルティングをするなら、さまざまな問題を解決したいと考えます。
しかし、中小企業の経営資源(ヒト・モノ・カネ)には限りがあります。なんでもかんでも取り組もうとすると、中途半端な結果に終わってしまいます。
コンサルタントは、あらゆる問題に対処しようとせず、重要な問題に焦点を絞って取り組むと良いでしょう。また、複数の問題に取り組むという場合、優先順位を付けること、各問題への経営資源の配分にメリハリを付けることが大切です。
留意点② クライアントと協創する
コンサルタントは企業経営に関する知識を持っています。一方、クライアントのメンバーにはあまり知識がありません。そのためコンサルティング・プロジェクトでは、先生であるコンサルタントが生徒であるメンバーに知識を授けるという関係になりがちです。
しかし、人は自分が決めたことは主体的に取り組みますが、他人から与えられたことに対しては、自分で決めたことほどの主体性は持ちにくい傾向があります。経営陣からプロジェクト参加を命じられたメンバーが受け身の姿勢で取り組んでいては、経営の難問を解決することはできません。 プロジェクトでは、コンサルタント主導でクライアントが経営改革を進めるプロセスを側面支援する、クライアントとコンサルタントが協力して新たな価値を創り出す(協創)というのが理想です。
留意点③ 成果実現にこだわる
コンサルティングで成果を実現するのは、容易なことではありません。もともと経営者の頭を悩ませてきた難問に挑んでいるということもありますが、プロジェクトの過程で、メンバーが業務多忙・業績悪化・抵抗勢力の出現といったトラブル・障害が起こるからです。
コンサルタントは、こうした事態に対処し、成果実現に向けて取り組みます。
ただ、コンサルタントが成果実現に向けてとことんこだわっているかというと、意外とそうでもないのが実情です。多くの経営者は、コンサルタントに成果実現をさほど強く要求しないからです。
よく経営者は、コンサルティングで成果が実現していなくても、「問題について新しい視点が得られた」「わが社の問題点が明確になった」「メンバーが大いに成長した」などと満足します。
しかし、本来コンサルタントとは、コンサルティングで問題が解決し、会社が発展してはじめてその価値が証明されるものです。経営者が満足しているからといって安心するのではなく、コンサルタントは成果実現にこだわる必要があります。
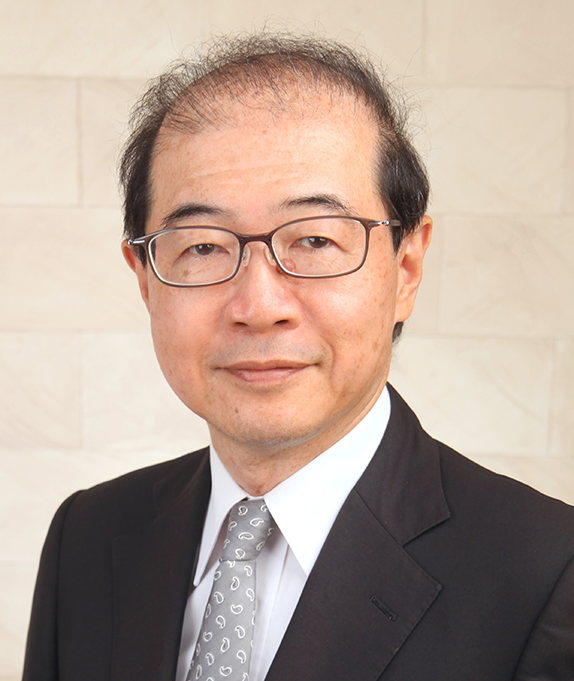
日沖 健
日沖コンサルティング事務所・代表
中小企業診断士、中小企業大学校・講師、産業能率大学・講師
1965年愛知県生まれ
慶応義塾大商学部卒、Arthur D. Little 経営大学院修了MBA with Distinction
日本石油(現・ENEOS)勤務を経て2002年より現職
経営戦略のコンサルティングと経営人材育成の研修を行う。また、中小企業大学校・中小企業診断士養成課程で後進のコンサルタントの育成にも注力している。
東洋経済オンラインに記事連載中、テレビ出演多数
著書(コンサルタント関係)
『税理士消滅時代を生き抜く ―コンサルタントへの進化戦略』
『コンサルタントを使って会社を変身させる法』
『コンサルタントが役に立たない本当の理由』
『中小企業診断士のリアル』
『中小企業診断士の独立開業のリアル』
『企業内診断士のリアル』
































