税務顧問から経営顧問へと脱皮する
<税理士がコンサルタントとして活躍するためには?③>

日沖コンサルティング事務所・代表
中小企業診断士、中小企業大学校・講師、産業能率大学・講師
日沖 健
6回に渡って税理士がコンサルタントとして活躍するためのポイントをお伝えするシリーズの3回目。今回は、税理士が税務顧問から経営顧問へと脱皮する方法を紹介します。
「悩みの委譲」に経営者は不満
あらゆる専門家の中で経営者にとって最も身近な存在である税理士は、経営者の格好の相談相手のはず。ですが、多くの税理士は税務顧問にとどまっており、「経営の困りごとを相談したい」というニーズには、ほとんど応えられていないのが実情です。
税理士が陥りがちなのは、次のような対話です。
法人税をいつ頃に納付しますか?
来月末を予定しています
そうですか。では、今日はこれくらいで…
あの…先生
?
資金繰りが悪くて、納税資金がちょっと足りないかもしれません
そうですか。いけませんねぇ
何とかなりませんか?
何とかと言われてもねぇ。たしか去年も同じようなことを仰っていて、結果的に大丈夫でしたよね
そうですが、去年と今年では事情も違いますし…
そんなに心配なら、銀行の担当者に相談してみたらどうですか
…
この税理士は、経営者にアドバイスしたつもりかもしれませんが、相談を受けて別の誰かに相談しろというのは、権限委譲ならぬ“悩みの委譲”です。
経営者は「聞くだけ無駄だった」と感じ、今後この税理士には税金のこと以外は相談しないでしょう。
税務相談から財務相談へ
では、税理士は、経営者とどういう対話をすれば良いでしょうか。
最終的には経営コンサルタントとして「経営相談」に乗りたいところですが、一足飛びには実現しません。「税務相談」から「財務相談」、さらに「経営相談」とステップアップしていくのが現実的です。財務とは、資金繰り・資金調達・資金運用・為替・リスク管理といった経営機能です。要は「カネ関係」です。税務も、この一部です。
多くの税理士は、「税金の話と資金の話は別物」と考えます。しかし、経営者にとっては「カネ関係」ということで同じ括りです。先ほどの例だと、次のような対話をします。
あの…先生。資金繰りが悪くて、納税資金がちょっと足りないかもしれません
決算書を見る限り、事業は順調のようですが。何か急な支出があったんですか?
決算後に幹部社員が退職し、退職金の支払いが発生しました。あと、若手・中堅でも3名退職者が出て、欠員補充のための採用コストがかさみました
退職金については、小規模企業共済に加入していましたよね。それだけでは足りなかったんですか?
ええ、足りませんでした
納税資金はいくら不足するんですか?
ええと、ちょっとわかりません
そうですか。資金繰り予定表を作っていませんでしたっけ
ええ、作っていますが、実にいい加減で
では、資金繰り予定表を作って必要資金額を確認することから始めましょう
この対話の後、税理士は経営者と協力して資金繰り予定表を作成します。この資金繰り予定表から資金不足額と必要調達額を見積ります。取引金融機関で既存の運転資金融資を借り増しすることができるか、納税資金ローンのような別の融資があるか、といった点を確認し、必要なら金融機関との融資交渉をサポートします。
税理士がこうした支援をしっかり実施すれば、経営者が直面している問題は解決します。これが「財務相談」です。
財務相談から経営相談へ
仮に、税理士のアドバイスのおかげで金融機関から追加融資を受けられたら、経営者は大満足でしょうか。
経営者は「先生のおかげで、助かりました。ありがとうございます!」と感謝します。しかし、まともな経営者なら、資金繰りの危機を逃れて「やれやれ」と一息ついているだけで、満足はしていません。「ずいぶん借入金が増えちゃったな。返済は大丈夫かな」と将来を心配しています。さらに、優れた経営者なら、「こんな綱渡りの経営をいつまでも続けていていいのだろうか。抜本的な改革が必要だ」と不満を募らせているでしょう。
そこで税理士は、クライアントの経営状態が良くなるように、「経営相談」を受けるようにします。財務だけでなく、調達・製造・販売・人事など経営の色々な面から問題点を探し出し、解決に向けてアドバイスをします。
この例だと、次のような対話をします。
決算後に幹部社員が退職し、退職金の支払いが発生しました。あと、若手・中堅でも3名退職者が出て、欠員補充のための採用コストがかさみました
幹部社員って業務部長の棚橋さんですか?
ええ、棚橋です。4月に急きょ退職しました
どうして退職したんですか?
確認できていません。本人は『充電期間を取って、また再就職します』と言っていましたが、どうでしょうかね。同業他社から引き抜かれたという噂もあります
幹部社員が理由もなく退職するって、かなりマズイですね。若手・中堅の3名は、どうして退職したんですか?
まあ普通に退職し、転職しました。こちらも理由は不明です。ただ、年功序列賃金で若手の給与水準が低く抑えられていることや権限移譲が進んでおらず、『働き甲斐がない』という不満を、他の若手社員からも耳にしています
そうですか。人の問題に取り組む必要がありそうですね
ええ、目先の業務に追われて、ずっと手つかずです
わかりました。まずは、喫緊の資金繰り対策について考えましょう。それが一段落したら、給与体系や権限移譲といった人の問題について、改革を一緒に取り組みませんか
この対話の後、まず税理士は経営者と協力して資金繰り対策を進めます。先ほどの「財務相談」です。それが一段落したら、従業員の実態調査をして問題点を明らかにし、給与体系の見直し・権限移譲・教育訓練といった対策を実施します。 対策がうまく行ったら、従業員の退職が減り、生き生きと働くようになり、会社が大いに発展するでしょう。これが「経営相談」です。
経営相談のために税理士が取り組むべきこと
経営相談を増やすために、また良き経営相談相手となるために、税理士は以下の点に留意します。
- 手始めは、経営者に会うことです。多くの税理士は、顧問先の経理担当者とは頻繁に連絡を取っていますが、経営者とは年1回確定申告のときだけ、というケースも多いようです。まず、顧問先の経理担当者だけでなく、経営者に会うようにしましょう。
- できれば、月次決算だけでなく、何か変化や出来事があったら会うようにします。たとえば、会社の周年にお祝いに行く、トラブルや災害があったらお見舞いに行く、イベントを開催したら顔を出す、人事異動があったら挨拶に行く、という具合です。
- 決算時に決算書類や確定申告書類などを作成し終えたら、決算書類・確定申告書類だけでなく経営分析(趨勢分析・ベンチマーキング・予実分析)をし、経営の問題点を分析してクライアントを訪問します。
- 実際の経営者との対話では、経営者の声に耳を傾け、経営者と一緒に問題について考えます。
双方向型の対話をする
このうち④について少し補足します。
経営者の声を聞き、経営者と一緒に考えるというのは、中小企業診断士の筆者にとってはごく当たり前のことですが、税理士の先生方にとってはなかなか難しいようです。税理士は、普段、税金について明るくないクライアントに「先生」として税金の知識を授ける立場だからです。
コンサルティングというと、コンサルタントがクライアントに知識を授けることだと思っているかもしれません。しかし、これは間違っています。コンサルタントは経営に関する専門知識を持っています。経営者は業界の事情や社内の状況を熟知しています。お互いが知恵を出し合って、協力して問題解決を進めるのが、本来のコンサルティングです。人は、自らの意思で「これをやるぞ!」と決めたことには、情熱を持って取り組みます。一方、他人から「これをやれ!」と命じられたことは、どんなに正しいことでも真剣に取り組むことが難しいものです。
コンサルティングは、実際に問題解決が実現して初めて価値を持ちます。コンサルタントがどんなに素晴らしい解決策をクライアントに伝授したとしても、クライアントがそれを我が事として取り組んで成果を実現しなければ、何の価値もありません。実際の問題解決ということを考えると、一方通行の知識の伝授よりも双方向型の対話の方が有効です。 税理士が双方向型で経営者と対話すると、「もっと経営に深く関与して欲しい」という話になります。単なる相談よりも経営に深く関与するアウトソーシング型コンサルティングについては次回、プロジェクト型コンサルティングについては次々回お伝えします。
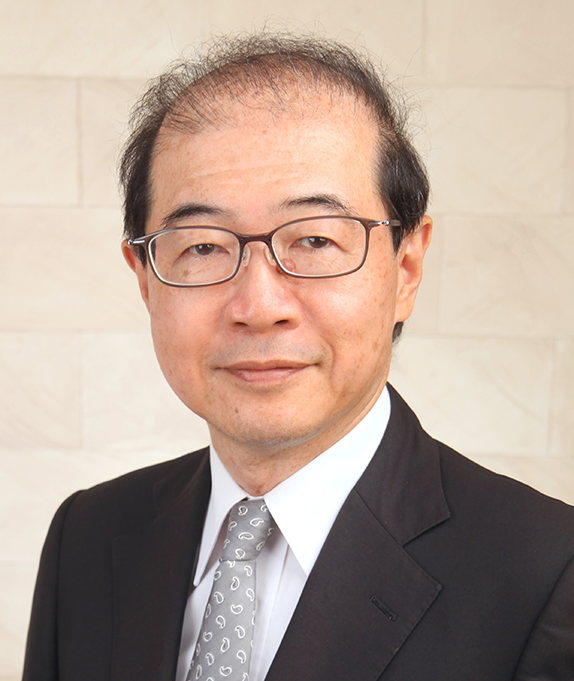
日沖 健
日沖コンサルティング事務所・代表
中小企業診断士、中小企業大学校・講師、産業能率大学・講師
1965年愛知県生まれ
慶応義塾大商学部卒、Arthur D. Little 経営大学院修了MBA with Distinction
日本石油(現・ENEOS)勤務を経て2002年より現職
経営戦略のコンサルティングと経営人材育成の研修を行う。また、中小企業大学校・中小企業診断士養成課程で後進のコンサルタントの育成にも注力している。
東洋経済オンラインに記事連載中、テレビ出演多数
著書(コンサルタント関係)
『税理士消滅時代を生き抜く ―コンサルタントへの進化戦略』
『コンサルタントを使って会社を変身させる法』
『コンサルタントが役に立たない本当の理由』
『中小企業診断士のリアル』
『中小企業診断士の独立開業のリアル』
『企業内診断士のリアル』






