「継続力」を身につけるための3ステップ:STEP3
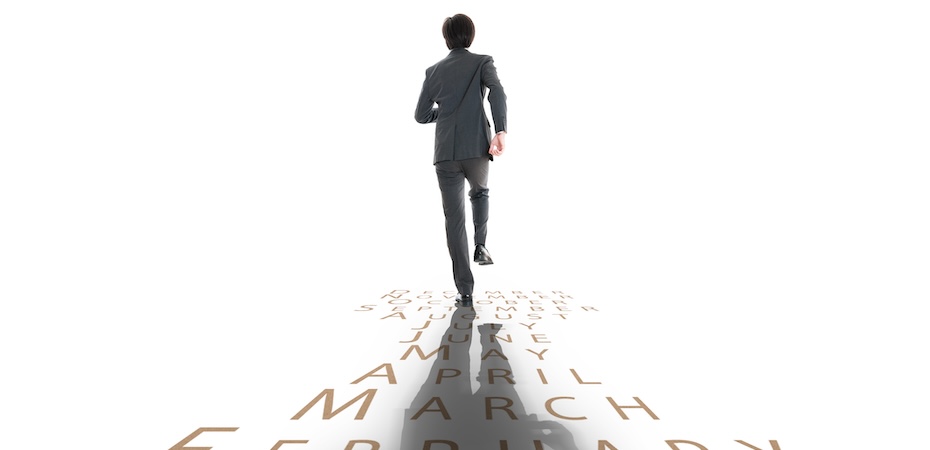
習慣化コンサルタント 習慣化コンサルティング株式会社 代表取締役
古川 武士
STEP3 倦怠期(飽きてくる)【22日~30日】
最後のステップは倦怠期でマンネリ化を感じやすい時期です。
つまり続けることに飽きてくるのです。徐々に続けることへの意味を感じなくなったり、物足りなくなったりして、「意味ないかも」「つまらないなあ」「飽きてきた」という言い訳が出てきやすくなります。しかしこの言い訳に負けないでください。これらの言い訳やマンネリ化は、実は習慣引力の最後の抵抗なのです。

いよいよ習慣化するぞというこのタイミングで、習慣引力が最後の抵抗をしてやめさせようとしているのです。このマンネリ化を乗り越えれば習慣化します。最後の山である倦怠期を上手に乗り越えましょう。
もちろん、飽きてくるタイミングは30日以降にやってくる人もいますが、この時期にマンネリ化への対策をしておけば今後いつ飽きが襲ってきても大丈夫です。倦怠期対策の大きなテーマは「変化をつける」ことです。対策を2つご紹介します。
1.変化をつける
同じことを続けていると、その単調さから徐々に飽きてきて、言い訳をしたり、意味を感じなくなり止めてしまいたくなったりします。そんなときは、小さな変化を持ち込むことをお勧めします。
私はウォーキングするときには、変化をつけるために「ウェアを変える」「ルートを変える」ことを実践しています。たとえば、第一週は自宅の周りのコース、第二週は最寄り駅コース、第三週は海沿いコース、第四週は川沿いコースと決めています。また、ウェアは合計5着持っていて、気分に合わせて変えています。 別の例を挙げると、貴乃花親方はウォーキング用のサングラスを30個ほど持っていて、毎回変えているそうです。これも続けるための工夫です。その他、英語の勉強であれば、勉強する場所を変える(自宅からカフェへ)、題材を英語テキストから好きな洋書に変えるなどもいいでしょう
但し、パターン化されたスタート時間や方法はむやみに変えないようにしてください。折角一定パターンが身につきつつあるのに台無しになってしまいかねません。先ほどのように場所を変えたり、題材を変えたり、ルートを変えたり、洋服を変えたりすることでマンネリ化を防ぐ工夫を考えてみてください。
2.次の習慣を計画する

2つ目に、次に習慣化したいテーマのプランをつくることも効果的です。
最初にお伝えした通り、良い習慣を増やすことで人生は変わっていきます。ですから、1つの習慣が身についたら、すぐに次の習慣に取り組めるように準備しておきましょう。最終ステップの倦怠期に次の習慣化プランをつくっておくことで、今の習慣を身につけることはあくまで通過点に過ぎなくなり、「さあこれを乗り切って次に行こう」と不思議とやる気が湧いてくるものです。
ここまで、習慣化するための方法を細かくご紹介してきました。3日坊主と嘆いていたあなたも、この方法を使えば続けやすくなると思います。
続けることはまさに「慣性の法則」と同じです。慣性の法則とは、「一度動き出した物体には運動し続けようとする力が働く」ということ。だからベビーステップで始めて、その行動を30日間続けることが重要なのです。そうすれば維持し続けようとする力が働き、習慣化していくのです。
もう1度、冒頭の話を思い出してみてください。続けるチカラがあれば、小さな変化が積み重なり大きな結果につながる。また、自分との約束を毎日守れることで、自信がつき輝く自分になれる。その結果、人間関係がよくなり、仕事で成果を上げることができ、健康や美にもうれしい変化が訪れます。
その為には、まず1つ続けたいテーマを決めて、ベビーステップから始めてください。それも明日からではなく、今すぐに。その一歩があなたの人生を変えるキッカケになっていくのです。是非頑張ってください。応援しています。

古川 武士
習慣化コンサルタント 習慣化コンサルティング株式会社 代表取締役
関西大学卒業後、日立製作所などを経て2006年に人材育成会社を設立。
コーチング・心理学を専門にこれまで企業研修・講演を通じて2万人以上の育成に携わってきた。
また、個人コンサルティングとしては経営者から若手ビジネスパーソン、主婦まで幅広く200名以上を支援している。多くの育成現場で痛感したことは、人が本当に変わっていくためには、
よい習慣を確実に身につける「続ける習慣」が重要と考え、オリジナルの習慣化理論とメソッドを開発。
独自メソッドを元に、企業研修、個人向けセミナー、コンサルティングを行っている。
著書に『続ける習慣』(現在7万部突破、韓国・台湾・中国で翻訳)『やめる習慣』
『すぐやる習慣』など計16冊で70万部を超えている。メディア掲載実績として、NHK、テレビ朝日、テレビ東京、朝日新聞、日経ビジネス、日経ウーマン、OZPLUS、プレジデント、
プレジデントファミリー、「企業と人材」等がある。
































