税理士報酬の相場感と価格決定のポイントとは?

税理士の報酬はおよそ20年ほど前に報酬規定が撤廃され、自由に設定できるようになりました。報酬設定の自由化は仕事に見合った報酬を自由に設定できるメリットがあります。
一方で、適正な報酬額を把握していないと、市場の相場にそぐわない報酬設定をしてしまうおそれもあります。
付加価値と工数、独自性を考慮しつつ、適正な料金体系を構築しなければいけません。
この記事では、報酬を決める際の大事なポイントや、報酬パターン、トラブル回避のための大切なポイントを詳しく紹介しています。
目次
税理士報酬の相場はどのように形成されるのか?実態を紹介

過去から現在に至るまで、税理士報酬の変遷と現状、税理士報酬を構成する内容など、詳しく説明します。
- 以前の報酬規定と撤廃後の現状
- 税理士報酬を形成する要素とは?
- 報酬額開示の状況
以前の報酬規定と撤廃後の現状
かつて税理士業界には日本税理士会連合会が定める報酬規定が存在していました。以前は報酬規定に沿ってクライアントへ報酬を請求していましたが、2002年の税理士法改正によって報酬規定は廃止され、現在では報酬の設定は自由化されています。
自由化されてからは、各税理士事務所ごとにサービス内容や専門性、地域性などを考慮し、独自の報酬体系を設定できるようになりました。
自由化の動きは価格競争の促進とともに、サービスの付加価値、差別化がより重視されるようになっています。
税理士報酬を形成する要素とは?
税理士報酬を決定づける要因を4つピックアップしました。
4つの要因が複合的に影響し、もっとも適切な報酬額が決定されます。
- 業務の難易度や複雑さと量…会社の売り上げ規模と取引量、従業員の数が多ければ多いほど記帳や申告の作業が増えるため、より複雑性が高くなります。その他には、相続税申告の土地や非上場株式の評価、特殊な取引の処理などがあると難易度がより高くなります。
- 提供するサービスの範囲と頻度…顧問契約の有無、訪問頻度、記帳代行の有無、コンサルティングなど付加価値サービスの提供によって変動します。
- 専門性の高さと経験…特定の分野に特化した専門知識や豊富な経験を持つ税理士は高い報酬を獲得できます。
- 地域性…都市部と地方では事務所の維持費と人件費が異なるため、報酬相場に差がでます。
報酬額開示の状況
税理士事務所の報酬の開示はそれぞれの事務所ごとに大きくことなります。
報酬の自由化によってWEBサイトに料金表を明示する税理士事務所も増えました。しかし、〇〇万円〜という表示や個別見積もりの提示とする事務所も少なくありません。
料金体系の明示は、顧客に安心感を与えますが、一律に表示しにくい案件もあるため、一概に明示が良いとも言い難いです。
報酬のトラブルを回避するには、契約する前に書面でサービス内容と報酬内容を提示した方が良いでしょう。
税理士が報酬を決める際に考えるべき主なポイント
税理士が報酬を決める場合に、考えるべき主なポイントを5つピックアップしました。
それぞれの詳細を説明します。
- サービスを提供する際の工数と時間的価値
- 顧問先の事業規模と複雑さ
- 提供できる付加価値と専門性
- 事務所のブランディングとポジショニング
- 競合事務所の調査と分析
サービスを提供する際の工数と時間的価値
税理士が報酬を決める際の、工数と時間的価値の提供はとても大事な要素です。
工数は記帳代行や申告書の作成、税務相談など、個々の業務に必要な具体的な時間のことを言います。工数に税理士が目標にする時間単価を乗じることによって、業務の適正な単価を導き出すことができます。
作業時間のみならず、業務を通じて提供する知識や経験、顧客の課題解決などの時間的価値も報酬に反映させた方が良いでしょう。
顧問先の事業規模と複雑さ
税理士の報酬は、顧問先の事業規模と課題の複雑性によって大きく変わります。
事業規模のものさしは、主に売上高と従業員数です。従業員が多ければ多いほど会計処理の仕訳数が多くなり、経理業務が複雑になります。
複雑性は、医療法人や建設業など、業界特有の会計処理、海外取引の有無、M&Aや事業承継などの特殊な業務の必要性のことです。
事業規模と複雑性によって税理士の報酬は高額になります。
提供できる付加価値と専門性
提供できる付加価値と専門性は、大事な差別化要因です。
単なる税務申告代行にとどまること無く、経営コンサルティング、資金繰り支援、事業承継、M&A支援、国際税務、IT導入支援など、顧客の経営課題を解決する付加価値の高いサービスが提供できれば、相応の高い報酬設定を設定できます。
また、医療や建設、飲食などの特定の業種や、相続税や事業承継税制など特定の税目に関する、深い専門知識や豊富な経験は顧客へ大きなメリットをもたらします。
一般的な税務サービスとは一味違う価値を提供できることから、より高い報酬額の設定が可能です。
事務所のブランディングとポジショニング
事務所のブランディングとポジショニングは、単なる価格競争に巻き込まれないための戦略です。
具体的には、高品質かつ専門性の高いサービスを提供する高価格帯事務所としてブランディングするのか、幅広い顧客をターゲットとした手頃な価格帯の事務所というポジションを確保するかによって、報酬設定が大きく変わります。
ターゲットとする顧客層へ提供する価値を明確にし、報酬額を一致させることで、より訴求力のある価格を提示できるでしょう。
競合事務所の調査と分析
競合事務所の調査と分析は、自分の事務所の報酬設定が相場からかけ離れていないか確認するために欠かせません。適正価格を判断するためにも大事な作業です。
競合調査は、同じ地域やターゲットとする顧客層が重なる競合事務所のWebサイトを確認することから始まります。
単に安さだけでなく、どのような付加価値を提供しているか、どのような専門分野で訴求しているのか、など深い分析が必要です。
競合の情報を確認することで、自分の事務所の立ち位置を明確にすることができ、独自の報酬設定を作り上げることができます。
具体的な報酬体系のパターンと実例
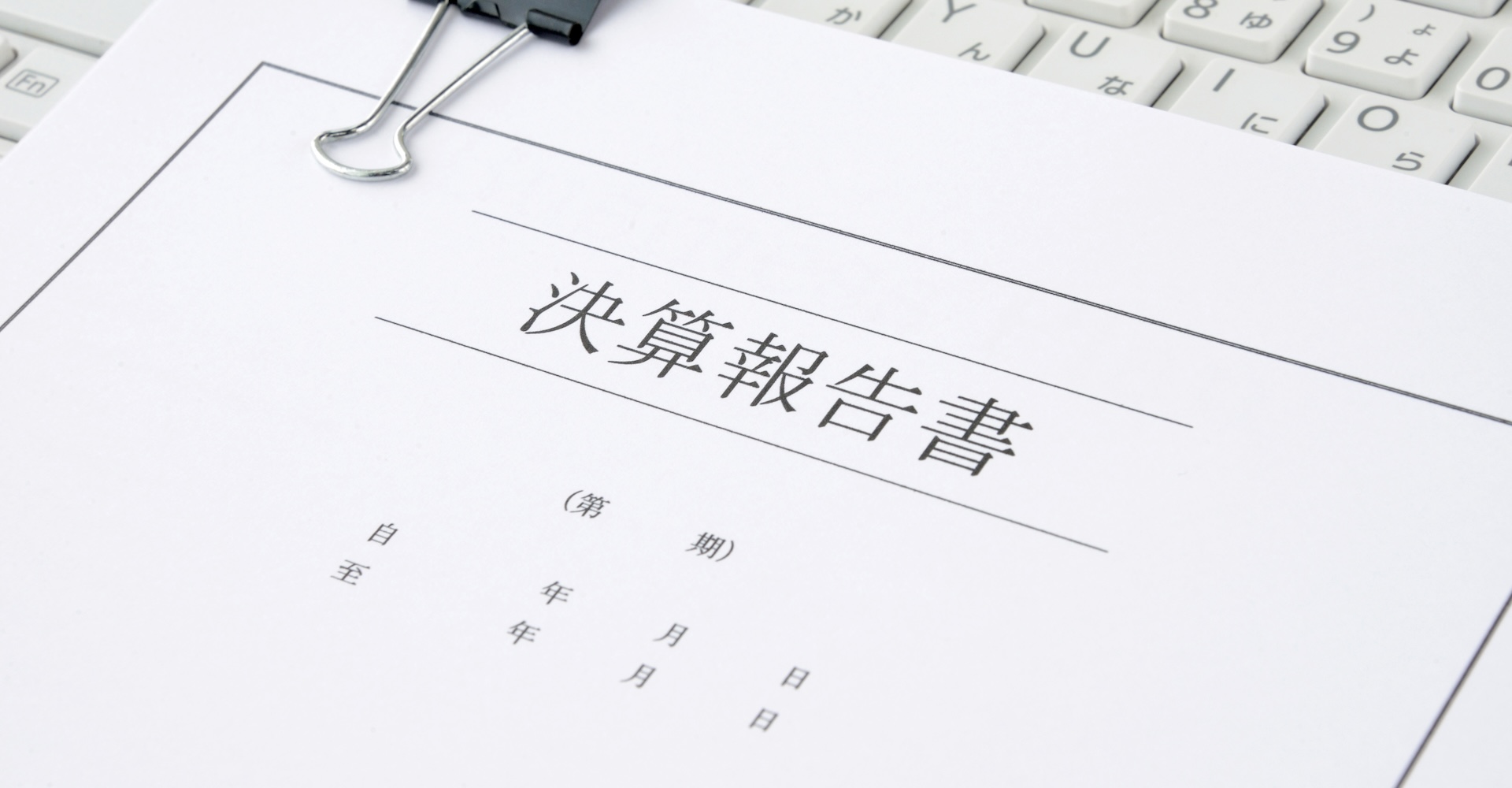
税理士の具体的な報酬体系のパターンを4つ紹介します。
- 月額顧問料+決算料のパターン
- 時間課金のパターン
- 成果報酬のパターン
- セット料金・パッケージ料金
月額顧問料+決算料のパターン
月額顧問料と決算料のパターンは、税理士報酬の中でももっとも一般的なものです。
月額顧問料は、毎月の税務相談、会計帳簿の確認、経営アドバイスなど、継続的なサービスに対して支払われます。
決算料は、年に一度の決算書の作成と法人税、所得税申告書作成などの決算業務全般に対してかかる費用です。
月額顧問料に決算料をプラスする報酬体系は、顧客が年間の費用を計算しやすく、税理士側も安定的収入が見込めるメリットがあります。
時間課金のパターン
時間課金制は、顧問契約のように継続的なサービスではなく、突発的な税務相談や特定の資料作成、スポットでのコンサルティング、税務調査の立会、セカンドオピニオンなど、業務量を確定しにくい場合や単発案件の際に用いられます。
顧客は必要なサービスを必要な分だけ利用できるメリットがありますが、事前の総額がわかりにくい点はデメリットです。
成果報酬のパターン
成果報酬パターンは、提供したサービスによって特定の成果が得られた場合にのみ、成果に応じた報酬を支払う報酬体系です。
具体的には、相続税申告における節税額の一部を報酬とするケースや、M&Aや事業承継における取引額の一定割合を報酬とするケース、税務調査において追徴税額を軽減できた場合に、金額の一部を報酬とするケースなどが挙げられます。
成果報酬は成果がでなければ報酬を支払う必要がない、顧客にとって合理的な形式です。一方で税理士側にとっては、成果が出なかった場合、それまでにかかった労力がすべて無駄になってしまう可能性があります。
相続税申告や事業承継、事業再生支援など、高度な専門性と具体的な結果が求められる業務で採用されることが多い報酬体系です。
セット料金・パッケージ料金
セット料金・パッケージ料金の報酬体系は、月次記帳、税務相談、給与計算、年末調整など複数のサービスを組み合わせて、定額の料金として提供する形式です。
顧客側は、提供されるサービス内容に対する費用が明確に提示されるため、予算を立てやすいメリットがあります。税理士側も、個別のサービスなど細かい見積もりをする必要がなくなるため、事務処理の効率化にも繋がります。
創業期の法人や個人事業主向けの「創業支援パック」や、特定の業種に特化した「医療法人向けパッケージ」など、特定のニーズを持つ顧客層に向けて設計されることが多い報酬体系です。
顧客とのトラブルを回避するためのポイント
顧客とのトラブルを回避するために抑えておきたいポイントを3つ紹介します。
- 報酬体系を書面にて明確に提示する
- 見積もりの段階で丁寧に説明する
- 定期的に報酬を見直す
報酬体系を書面にて明確に提示する
報酬体系の書面での明確な提示は、トラブル回避のために欠かせません。口頭のみの説明では後々、言った言わないのトラブルに発展する可能性が高いです。
書面は、顧問契約書や委任契約書などの体裁を取り、月額顧問料、決算料、記帳代行料などの各サービスの料金、算出基準、支払い期日、そして追加業務が発生した場合の料金規定などを詳細に明記します。
書面による透明性の確保は、お互いの信頼関係構築のために欠かせない手続きです。
見積もりの段階で丁寧に説明する
単に見積書を提示するだけでなく、どのようなサービスを提供するのか、費用が発生する理由の具体的な説明も大切です。
たとえば、記帳代行料であれば「毎月〇〇件の仕訳を処理し、試算表を作成する」といった具体的な業務範囲を伝えます。
また、追加費用が発生するケースの共有も欠かせません。丁寧な説明によって、誤解や不満を回避することができ、健全な信頼関係を築くことができます。
定期的に報酬を見直す
顧問先の事業の状況次第では、税理士に求められる業務量が増減することがあります。良好な関係を維持するには、その時点の業務量に合わせた定期的な報酬の見直しも考えた方が良いでしょう。
たとえば、顧問先の売上の大幅な増加や、M&Aや事業承継など新たなプロジェクトが発生した場合、当初の契約内容ではカバーしきれない業務が発生する可能性があります。
業務量の増加によって新たな費用の請求が必要になった場合は、業務量の増加を双方で認識し、納得の上で報酬の見直しを提案しなければいけません。
まとめ
税理士の仕事に対する報酬は、適正なものでなければいけません。とはいえ、市場の相場と大きくかけ離れていると、新規案件の獲得もままならないでしょう。
自分のスキル、専門性、独自性を棚卸したうえで、競合事務所の調査を進めつつ、ちょうど良い価格帯で報酬体系を確立する必要があります。
幅広い案件に対応するためには、柔軟な料金設定も必要です。ターゲットとする顧客層と目指すべき業務のあり方をよく考えたうえで、適正な料金体系を構築しましょう。
 オンライン研修・eラーニング
オンライン研修・eラーニング
e-JINZAIで
社員スキルUP!
- e-JINZAI for account(会計事務所向け)
- e-JINZAI for business(一般企業・団体向け)
- 今ならe-JINZAIを2週間無料でお試しいただけます!

税理士.ch 編集部
税理士チャンネルでは、業界のプロフェッショナルによる連載から
最新の税制まで、税理士・会計士のためのお役立ち情報を多数掲載しています。
運営会社:株式会社ビズアップ総研
公式HP:https://www.bmc-net.jp/






