弁護士と公認会計士のダブルライセンスは需要ある?メリットや稼ぎ方も紹介

「公認会計士と弁護士のダブルライセンスの需要は?」
「取得難易度に見合うメリットはあるんだろうか?」
公認会計士と弁護士のダブルライセンスと聞いて、このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。ダブルライセンスが本格的に有利に働くのは独立後です。他の事務所との差別化を図る時に、最高のアピールポイントとなります。
この記事では、公認会計士と弁護士のダブルライセンスについて、詳しく説明しています。ダブルライセンスのメリットなど、気になる方はぜひ記事内容をご確認ください。
目次
公認会計士と弁護士のダブルライセンスの需要
公認会計士は医師や弁護士とともに日本の三大国家資格と呼ばれるほど難易度の高い資格です。弁護士と公認会計士のダブルライセンスは、三大国家資格のうち2つを取得することになるため、付加価値の高い人材として評価されます。
ダブルライセンスを持っている人自体が稀な存在であるため、希少性の高い人材として認められることは間違いありません。
ダブルライセンスをもつ人材は、色々な場面での活躍が期待されますが、時にM&A分野においてのニーズは特に高いです。弁護士と公認会計士のライセンスを持っていれば、法務調査と財務調査を1人で請け負うことができます。本来2人で行うべき業務を1人でこなせるわけですから、M&A分野において需要が高いのはいうまでもありません。
公認会計士と弁護士のダブルライセンスのメリット

ダブルライセンスの具体的なメリットを4点紹介します。
- 財務と法務の両方からサポートできる
- 転職市場で有利になる
- 双方の専門性が必要な業務に対応できる
- 業界での人脈を広げやすい
- クライアントからの評価と信頼を獲得しやすい
財務と法務の両方からサポートできる
企業や個人が抱える問題の多くは、法律と会計の問題が複雑に絡まり合っています。具体的には、企業の民事再生の手続きにおいては、裁判所での法的手続きの中で法律の知識が必要とされます。そして再生案を検討するうえでは、会計や税務の知識が欠かせません。
一般的には弁護士と公認会計士が携わる案件ですが、ダブルライセンスをもつ人材なら1人で二つの仕事をまとめて引き受けることも可能です。
クライアントに対しても、一つの窓口で対応できることから、信頼性も高まります。
転職市場で有利になる
特にM&Aを多く扱う法律事務所への転職においては、即戦力の人材として高い評価を得ることができます。他にはダブルライセンスをもつコンサルタントとしてのポジションや、経営企画と法律の両方に携わるポジションに応募する際にも有利です。
企業内弁護士、監査法人、コンサルティングファームなど、幅広い選択肢にて、高待遇の求人に応募することができます。不正調査やM&A、訴訟関連業務など、高度な専門性と多角的な視点が求められる領域においては、特に高い評価を得られるでしょう。
双方の専門性が必要な業務に対応できる
企業案件では、財務と法務が密接に関わっていることから、簡単には切り離せません。知識がない状態で、なんとか対応しようとしても時間の無駄に終わることは容易に想像できます。公認会計士は法律の知識が乏しく、弁護士が必ずしも数字に強いとは言い切れません。
そんな時に、弁護士と公認会計士の資格を持つ人がいれば、お互いの苦手分野を補完しつつ、2つの専門性を活かして業務を進めることができます。
業界での人脈を広げやすい
横の繋がりが深い士業業界において、ダブルライセンスを保有している人は、弁護士業界と公認会計士業界の2つの分野で人脈を拡大できます。両方の業界で人脈があれば、ビジネスチャンスは拡大する一方です。
例えば公認会計士の知り合いから法律案件を紹介してもらえるケースがありますし、弁護士の知り合いから財務調査を紹介してもらえるケースもあります。
弁護士と公認会計士の資格を両方とも持っている人は少ないため、それぞれの業界の専門知識が必要になる仕事があれば、ピンポイントで指名を受けることも考えられます。
クライアントからの評価と信頼を獲得しやすい
ダブルライセンスというインパクトは大きなものです。難しい資格を2つも持っているとなると、最初からクライアントからの高い信頼を得ることができます。
クライアントからの評価や信頼を得やすくなると、案件が獲得しやすくなり、ビジネスチャンスの拡大が期待できます。
ダブルライセンスをもつ人材への依頼は、期待を超える仕事内容とともに依頼の手間も省けるため、クライアントにとっても良いことが多いです。
弁護士による公認会計士取得の難易度と注意点
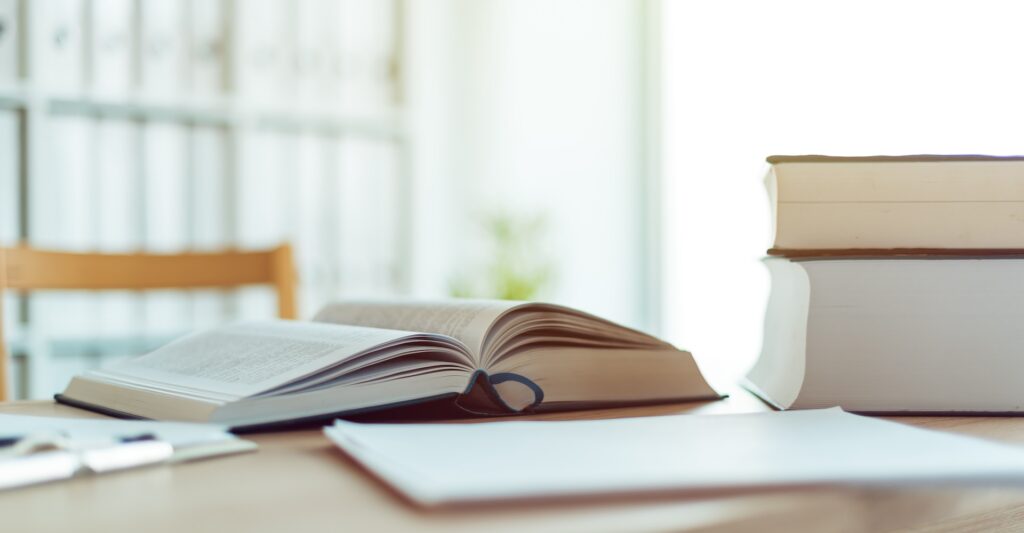
弁護士として働きながら公認会計士を目指すケースと、公認会計士として働きながら弁護士を目指すケースがありますが、ここでは弁護士が公認会計士を目指すパターンを紹介します。
- 公認会計士の難易度と科目免除
- 弁護士として働きながら公認会計士資格の取得ができる
- 登録までに年数がかかる
公認会計士の難易度と科目免除
最近の公認会計士試験の合格率は10%前後で推移しています。一方で、司法試験の合格率は22%〜33%程度です。司法試験の合格率が低く、公認会計士試験の合格率が高いのは、受験資格の前提条件が異なるためです。
公認会計士の試験は、受験資格がないため誰でも受験できますが、司法試験は法科大学院を修了した人、もしくは予備試験に合格した人のみが受験できる仕組みです。あらかじめ厳しい条件の中で、受験資格を獲得しているため、本試験での合格率が高くなっている、というわけです。
一般的には、司法試験の予備試験に比べると、公認会計士の試験はやや難易度が低いと言われています。公認会計士の試験に備える時間があれば、弁護士の人が公認会計士になるのは十分にあり得ることです。
なお、公認会計士の試験には、一部科目免除制度が設けられています。弁護士資格も該当するため、科目免除が受けられるメリットもあります。
弁護士として働きながら公認会計士資格の取得ができる
公認会計士が弁護士の資格を取得する場合、働きながら取得を目指すのは現実的に不可能です。勉強が大変なことに加えて、弁護士になるための司法修習が9時〜17時と決められているため、監査法人や会計事務所に勤務している状況では対応できません。
弁護士として公認会計士の資格を取得する場合は、実務経験を非常勤の監査業務にて習得できます。弁護士として公認会計士の資格を取得する場合は、公認会計士ほどの苦労はないでしょう。
登録までに年数がかかる
公認会計士として活躍するには、試験合格後に2年間もしくは3年間の補習所通学を経て修了考査に合格しなければいけません。登録までの年月が必要で、その間は弁護士の仕事と合わせて公認会計士としての実務を積み上げる必要があります。
公認会計士の試験に一発合格できるとは限らないため、余計に年月がかかる可能性は認識しておいた方が良いでしょう。労力と見返りを含めて、ダブルライセンスを取得するかどうか、しっかりと考えた方が良いかもしれません。
ダブルライセンスで高年収を狙うには?
公認会計士と弁護士のダブルライセンスなら、高年収を実現できるのでは?と考える人も多いのではないでしょうか。
ここでは、弁護士と公認会計士の年収を比較しつつ、ダブルライセンスと年収の関係性を考察してみます。
- 弁護士と公認会計士の年収の比較
- 年収アップは働き方次第
弁護士と公認会計士の年収の比較
厳密には年収の個人差があるため、正確な比較は難しいのですが、参考としてそれぞれの業界で最高と言われている五大法律事務所とBIG4監査法人の初任給を比較してみます。
五大法律事務所の年収は、1年目から1,000万円〜1,200万円に及びます。BIG4監査法人は、1年目のスタッフクラスで年収450万円〜650万円が目安です。
五大法律事務所の弁護士の年収の高さには、入所難易度が関係しています。公認会計士の多くは試験に合格するとBIG4監査法人へ就職する流れがありますが、五大法律事務所への入所はそう簡単なものではありません。弁護士の中でも選ばれた人しか就職できません。
五大法律事務所以外の法律事務所で働く弁護士の年収が、初年度600万~700万円ということを考えると、弁護士の方が個々の能力による年収の差が大きいとも言えます。
年収アップは働き方次第
弁護士が公認会計士の資格を取得したとしても、法律事務所で仕事をする以上、他の弁護士と比べて給料が大幅に上がるということはありません。
弁護士は基本的に個人事業主であり、仕事の獲得方法の自由度は高いです。したがって、ダブルライセンスを活かして年収を上げたい場合は、法律関連の案件に加えて会計領域での仕事を受ける、という方法があります。
ダブルライセンスを活かして高年収を狙いたい場合は、M&Aを多く扱う法律事務所への就職が理想的です。ダブルライセンスの良さを遺憾無く発揮できるでしょう。
またダブルライセンスを差別化ポイントとして、独立する選択肢も有効です。ダブルライセンスをもつ人材は希少なので、他の法律事務所との大きな差別化ができます。
まとめ
ダブルライセンスを活かして高所得を狙う場合は、個人裁量がある法律事務所へ勤務するか、独立開業で他の法律事務所との差別化を図る方法があります。
基本的には弁護士業務をメインとして、付随業務に財務や会計の仕事を受けるイメージです。
クライアントは弁護士と公認会計士を同じ人に任せることができるため、報酬費用を抑えることができます。窓口の一元化もできるため、信頼も得やすいでしょう。
弁護士と公認会計士のダブルライセンスは、かなりの労力を要します。自分にとって本当にメリットがあることなのか、よく考えたうえで挑戦するようにしましょう。
 オンライン研修・eラーニング
オンライン研修・eラーニング
e-JINZAIで
社員スキルUP!
- e-JINZAI for account(会計事務所向け)
- e-JINZAI for business(一般企業・団体向け)
- 今ならe-JINZAIを2週間無料でお試しいただけます!

税理士.ch 編集部
税理士チャンネルでは、業界のプロフェッショナルによる連載から
最新の税制まで、税理士・会計士のためのお役立ち情報を多数掲載しています。
運営会社:株式会社ビズアップ総研
公式HP:https://www.bmc-net.jp/
































