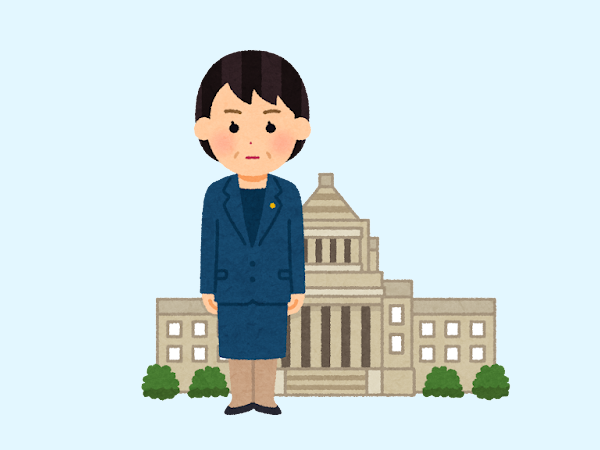積極財政と緊縮財政とは。日本はどちらへ舵を取るべきか

参議院選挙を前にして、各政党が打ち出す経済政策が注目を集めました。その中で、論争の的となっているのが「積極財政」か「緊縮財政」かという財政運営の方向性です。物価上昇と景気の先行き不透明感が交錯する今、どのような財政姿勢を取るかによって、国民生活や企業経営の現場に与える影響は決して小さくありません。
この論点は、単に財政支出の規模をめぐる議論ではなく、日本の経済的な体力、財政の持続可能性、そして国家としての将来像にまで深く関わるテーマです。特に、経営判断をサポートする職務に就く皆さまにとって、これらの政策がもたらす中長期的影響を正しく見極めるのは重要だといえます。
本稿では、積極財政と緊縮財政それぞれの基本的な理念と主張を紹介し、近年の日本がどのような方針を採ってきたかを振り返ったうえで、今後の財政運営のあり方について多角的に考察していきます。
目次
積極財政とは何か

積極財政とは、経済が停滞しているときに、政府が財政支出を拡大し、景気回復を図ろうとする政策です。これはケインズ経済学に基づくアプローチで、減税や公共事業、給付金の支給などを通じて有効需要を創出し、民間経済の落ち込みを補うという考え方に立脚しています。高校の教科書にも出てきますが、1930年代世界恐慌から脱出するためにアメリカのルーズベルト大統領がとったニューディール政策がその有名な例として挙げられます。
ニューディール政策では、公共事業(ダムの建設)による雇用創出や、銀行制度改革、農業調整法による価格安定策、社会保障制度の導入などが実施され、経済の再建と国民生活の安定が図られました。積極財政ではこのようにインフラ等への公共投資や教育・医療に対する財政支出を通じて、民間消費や設備投資の活性化を目指します。こうした施策が、賃金の上昇から可処分所得の増加へとつながっていくわけです。このアプローチは、短期的に財政赤字が拡大するリスクを伴いますが、経済成長によって税収が増加し、中長期的には財政の健全性も回復するという見通しに基づいています。
また、積極財政は景気回復の効果に加え、格差是正や社会的安定にも資するという評価があり、所得の再分配や地方経済の活性化といった観点からも、有効な政策手段として位置づけられています。
緊縮財政とは何か
一方、緊縮財政とは、政府が財政支出を抑制し、財政赤字や政府債務の増加を防ごうとする政策です。こちらは主に新古典派経済学に基づいており、過度な支出はインフレや金利上昇、通貨安を招くとして、財政規律の維持を最優先します。
緊縮財政の例として挙げられるのが、1990年代後半のカナダです。当時のカナダは財政赤字と政府債務の拡大に直面していましたが、1995年に自由党のジャン・クレティエン政権が大規模な歳出削減と公務員削減を実施。社会保障や地方交付金も見直され、財政支出の構造改革が進められました。
その結果、数年でプライマリーバランスを黒字化し、金利低下と投資拡大を呼び込み、構造改革によって景気も回復基調に転じました。IMFから「模範的」と評価された事例です。
このように緊縮財政では、増税や社会保障給付の見直し、公共事業の削減といった手段を用いて財政収支の均衡を図ります。これは短期的には景気を抑制する方向に作用する可能性がありますが、長期的には国債市場の信認維持や金利の安定、通貨の信用保持などに貢献するとされています。
加えて、財政破綻リスクの回避は国際的な信用の維持とも直結しており、国家としての責任ある姿勢を内外に示す手段でもあるとされます。したがって、緊縮財政は単なる数字合わせではなく、「財政の持続可能性」を重視する政策だといえるでしょう。
近年の日本はどちらの政策をとってきたのか
ここ数十年の日本の財政運営は、景気動向や社会状況に応じて積極財政と緊縮財政を使い分ける、いわば「選択的併用」の形を取ってきました。1997年の消費税5%への引き上げを皮切りに、2014年には8%、2019年には10%へと段階的に引き上げられましたが、これらはいずれも財政再建を目的とした緊縮的措置といえます。
また、社会保障制度改革の名の下に医療や介護の自己負担率が引き上げられ、年金支給開始年齢の見直しも進められてきました。これらはすべて、将来的な財政負担を軽減することを意図した政策です。税と社会保障の一体改革という名目のもとで、着実に歳出抑制が進められてきたと言ってよいでしょう。
一方で、コロナ禍では例外的に大規模な財政出動が行われました。2020年には全国民への一律10万円の特別定額給付金が支給され、持続化給付金、家賃支援給付金、雇用調整助成金の拡充といった形で、前例のない規模の財政支出が実施されました。ただし、これらはあくまで緊急避難的な措置であり、恒常的な積極財政に転換したわけではありません。
積極財政派の主張
積極財政派は、日本が長期にわたりデフレや低成長に苦しんできた背景には、明らかに需要不足が存在しており、それを政府が補わない限り、経済は回復しないと主張します。
2025年6月23日、れいわ新選組の山本太郎代表は、参院選の公約発表会において「消費税の廃止こそが、最も効果的な可処分所得増加策だ」と強調しました。また「失われた30年」を取り戻すために、全国民への10万円給付の継続、生活困窮者への直接支援、公共住宅の整備などを含む大規模な支出計画を掲げています。
さらに、参政党の神谷宗幣代表も、2025年7月3日の記者会見で「日本経済はまだ脆弱であり、日銀が国債購入を減らせば、政府の政策余地が奪われる」と発言。政府・日銀の協調による財政出動の必要性を訴えました。
自民党内では、2021年から高市早苗議員が「PB(プライマリーバランス)黒字化目標の凍結」を訴え、「経済成長があってこそ財政健全化が可能になる」と主張。成長戦略と財政支出は矛盾するものではなく、むしろ連動すべきだという立場を取っています。
彼らは共通して、日本の国債はほぼすべて円建てであり、国内の投資家や日本銀行が保有しているため、国債価格が暴落するような財政危機は考えにくいとしています。そのため、むしろ現在の需要不足を放置することこそが、将来的に税収減や社会不安を引き起こすと警鐘を鳴らしているのです。
緊縮財政派の主張
一方、緊縮財政を主張する立場は、日本の財政赤字が異常な水準に達している現状に強い危機感を抱いています。
財務省主計局の宇波次長は、2025年3月4日の衆議院財務金融委員会で「財政の持続可能性を確保するためには、安易な支出拡大は避けなければならない」と答弁しました。また、「PB黒字化目標は国際的信認を保つうえで不可欠である」として、引き締め政策の継続を強調しています。
岸田前首相も、同年5月19日の国会で「金利が上昇すれば、国債の利払いが財政を圧迫し、他の政策的支出に支障が出る」と発言。6月9日の記者会見では、「財政規律を失えば、長期金利の上昇や通貨の不安定化が生じかねない」と語り、緊縮路線の必要性を再確認しました。
緊縮派は、特に少子高齢化が進む日本においては、社会保障費の増加が確実である以上、いまのうちに支出抑制と税収確保の体制を整えておかなければ、将来的に財政運営が立ち行かなくなるという懸念を抱いています。彼らにとっては、「将来世代にツケを回さない」という倫理観が、すべての政策判断の根底にあるのです。
いま日本はどちらにすべきなのか?

日本経済はいま、緩やかな物価上昇と実質賃金の伸び悩みというねじれた構造の中にあります。金利は上昇の兆しを見せており、日銀の金融政策の正常化も段階的に進みつつありますが、それがただちに民間需要の拡大や賃金上昇にはつながっていないのが現状です。
このような状況下で財政支出を急激に絞れば、景気後退を招くリスクが高まります。むしろ今は、医療・介護・教育・インフラ・防災など、将来の生産性や安全性に資する分野への戦略的な投資を継続すべき局面です。そのうえで、景気が自律的に回復し、税収が安定してから、段階的に財政再建へと転じていくのが現実的であるかに見えます。
かといって、人口が想像を超えるスピードで減少していけば、税収は減り需要も減り景気も後退していくのは計算で予測可能な事象です。支出もこれまで通りというわけにはいかなくなるのが自明の理であり、かといって足りなくなった分をすべて国債で賄う政策も持続可能とはいいがたいものがあります。
加えて、グローバルな経済環境の変化や地政学的リスクも念頭に置く必要があります。世界的なインフレ圧力やサプライチェーンの混乱、エネルギー価格の高止まりといった要因は、国民生活に直接的な影響を与えています。
こうした外部環境に柔軟に対応するためにも、国内経済の基盤を安定させる戦略的な財政政策が不可欠といえます。
まとめ
積極財政と緊縮財政という2つの立場は、単なる政策手法の違いではなく、「日本の経済と財政の現状をどう認識するか」という立場の違いに根ざしています。需要不足を最大の課題とみるなら積極財政、債務膨張を主たる問題とみるなら緊縮財政という選択になります。
重要なのは、どちらか一方に偏るのではなく、局面に応じて柔軟に財政運営の舵を切ることです。財政支出の効果や限界を冷静に見極めつつ、経済全体の成長と安定を両立させる設計が必要です。
つまり、緊縮財政と積極財政のどちらも必要なのであり、構造改革による景気対策をとりつつPB黒字化へ向けた道筋を考えていくのがよいのではないでしょうか。
税務に携わる皆さまにとっても、こうした政策の背景や動向を正しく理解し、経営者への適切な助言が、今後ますます求められる時代に入っています。経済・財政の動向を読み解く目と、柔軟に対応する思考の両輪が、これからの実務において極めて重要となることでしょう。
 オンライン研修・eラーニング
オンライン研修・eラーニング
e-JINZAIで
社員スキルUP!
- e-JINZAI for account(会計事務所向け)
- e-JINZAI for business(一般企業・団体向け)
- 今ならe-JINZAIを2週間無料でお試しいただけます!

税理士.ch 編集部
税理士チャンネルでは、業界のプロフェッショナルによる連載から
最新の税制まで、税理士・会計士のためのお役立ち情報を多数掲載しています。
運営会社:株式会社ビズアップ総研
公式HP:https://www.bmc-net.jp/