流動資産と流動負債とは?企業分析への活用法や注意点を解説

企業が保有する資産や負債は、企業会計原則の「貸借対照表原則」に基づき、資産については流動資産・固定資産・繰延資産に、負債については流動負債・固定負債に区分して、貸借対照表に表示しなければなりません。
流動資産と流動負債は、流動性の高い資産や負債を指し、イメージとして「すぐに支払いに使えるもの」や「すぐに支払わなければならないもの」と考えるとわかりやすいでしょう。
これらは企業の支払い能力を測る材料となり、安全性分析にも活用することができます。
本記事では、流動資産と流動負債について、どのような項目が該当するのかを整理し、それらの数値から企業の安全性をどのように分析できるのかを解説していきます。
目次
流動資産とは何か
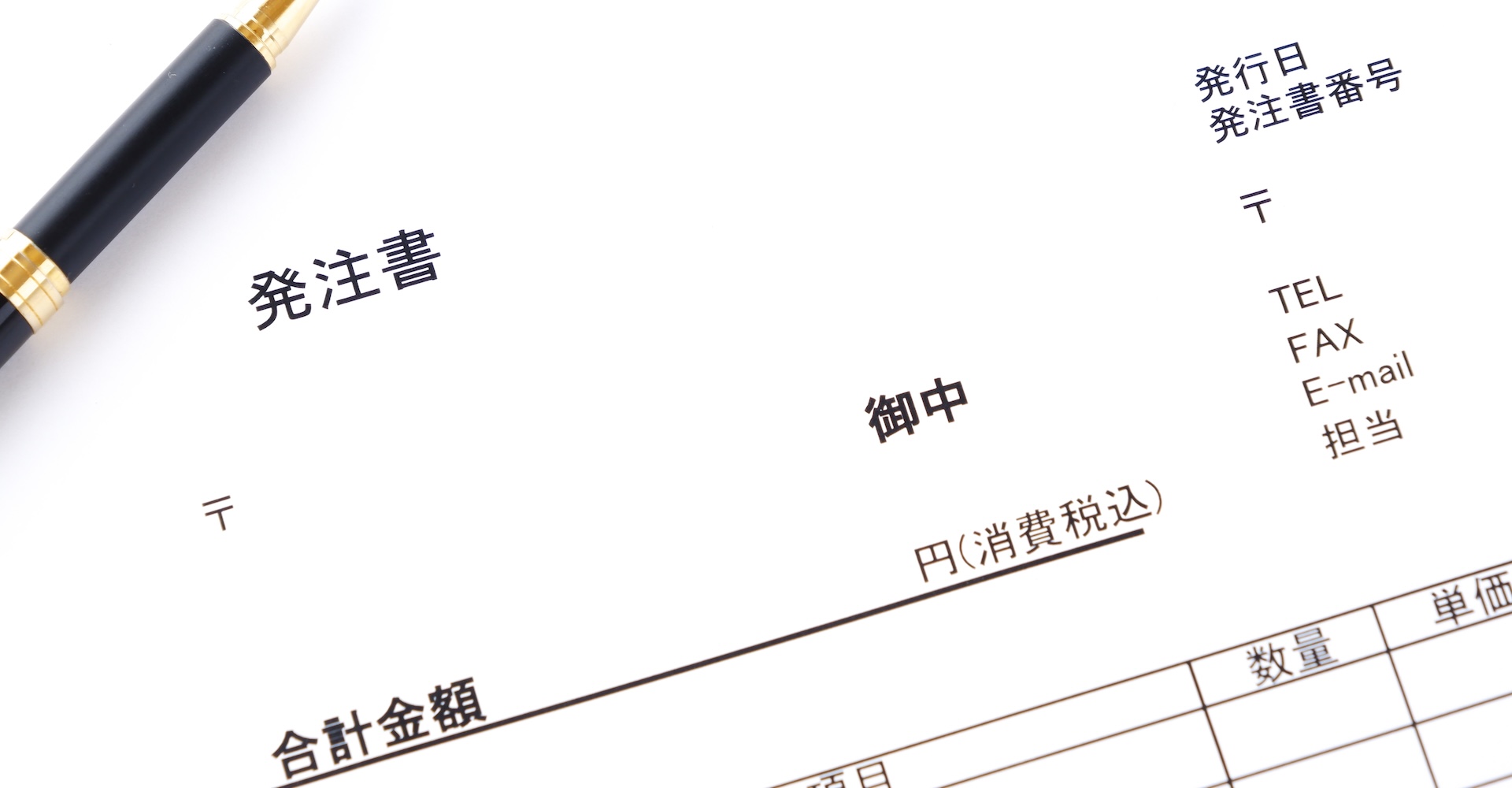
流動資産とは、流動性が高く、短期間で現金化しやすい資産のことを指します。
企業が保有する資産のうち、通常の営業活動の過程にある資産や、1年以内に現金化できる資産が、流動資産に分類されます。
通常の営業活動の過程にある資産とは、「仕入れ→製造・販売→回収」というサイクルに含まれる資産で、商品や売掛金などが該当します。流動資産と固定資産を分ける基準の一つであり、これを「正常営業循環基準」といいます。
一方、この正常営業循環基準に当てはまらない資産であっても、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に現金化できるものは流動資産に含まれます。これを「1年基準」あるいは「ワン・イヤー・ルール」と呼び、固定資産との区分基準の一つとなっています。
「正常営業循環基準」と「1年基準」のいずれにも該当しない資産は、流動資産ではなく固定資産として区別されます。
流動資産の範囲
流動資産に該当する主な資産は、以下のとおりです。
| 流動資産に該当するもの | 内容 |
| 現金及び預金 | 現金、預貯金(普通預金、当座預金、満期が1年以内の定期預金など) |
| 受取手形 | 通常の営業取引から生じた約束手形、為替手形 |
| 売掛金 | 通常の営業取引から生じた未収金 |
| 電子記録債権 | 通常の営業取引から生じた、電子化された金銭債権 |
| 契約資産 | 物やサービスを提供する対価として顧客から支払いを受ける権利(受取手形・売掛金以外のもの) |
| 有価証券 | 売買目的有価証券または1年以内に満期の到来する有価証券 |
| 商品 | 販売目的で保有する資産 |
| 製品・半製品・仕掛品・原料及び材料 | 製造して販売する資産 |
| 貯蔵品 | 消耗品など |
| 前渡金(前払金) | 商品などの購入のために前払いした金額 |
| 前払費用、未収収益 | 1年以内に費用や収益となるもの |
| リース債権、リース投資資産 | 通常の営業取引で発生したものや1年以内に入金の期限が到来するもの |
| その他1年以内に現金化できるもの | 1年以内に現金化できるもの(短期貸付金、立替金など) |
流動負債とは何か
流動負債とは、企業が負う債務のうち、すぐに履行しなければならないもののことです。
流動負債もまた、「正常営業循環基準」と「1年基準」で固定負債と区別されます。
したがって、営業活動の過程で発生した仕入れ債務や、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払期限が到来する負債が、流動負債に該当します。
流動負債の範囲
流動負債に該当する主な負債は、以下のとおりです。
| 流動負債の範囲 | 内容 |
| 支払手形 | 通常の営業取引で発生した手形債務 |
| 電子記録債務 | 通常の営業取引で発生した金銭債務 |
| 買掛金 | 通常の営業取引から生じた未払金 |
| 契約負債・前受金 | 物やサービスを提供する義務の対価として顧客から支払いを受けているもの(またはその期限が到来しているもの) |
| 引当金 | 1年以内に使用される見込みのあるもの(賞与引当金など) |
| 未払金・預り金 | 短期間で支払われるもの |
| 未払費用、前受収益 | 1年以内に費用や収益となるもの |
| リース負債 | 1年以内に期限が到来するもの |
| 資産除去債務 | 1年以内に履行されると認められるもの |
| その他1年以内に履行されるもの | 1年以内に支払い・返済されるもの(短期借入金など) |
流動資産と流動負債の活用方法
流動資産と流動負債を活用することで、簡単な企業分析が可能です。
企業分析は、主に企業の収益性、安全性、成長性などを明らかにするために行われますが、このうち、流動資産と流動負債から把握できるのは「安全性」になります。
企業の安全性を分析する「流動比率」とは
貸借対照表に表示された流動資産と流動負債の額から、その企業の支払い能力を測る「流動比率」を計算することができます。
【流動比率の計算式】
流動比率=流動資産÷流動負債×100%
流動負債よりも流動資産のほうが大きければ、流動比率は100%を超えます。目安としては、120%以上であれば安全性の高い企業とされ、100%未満であれば支払い能力にリスクがあると考えられます。
例えば、流動資産600万円・流動負債400万円であれば、流動比率は150%となり比較的安全です。一方、流動資産200万円・流動負債250万円であれば流動比率は80%となり、危険水域と判断されます。
流動比率は高いほど良いのか?
流動資産と流動負債から計算できる流動比率は、その企業の安全性を手軽に把握できる点が利点です。
しかし、便利な反面、その数値が「高い」または「低い」だけでは十分に評価できません。たとえば、流動比率が高すぎる場合も注意が必要です。
その場合は、企業の資金が遊休化し、設備投資や人材育成など成長のための投資に十分活用されていない可能性があります。また、流動比率が安心できる水準であっても、流動資産の中身に目を向けることが重要です。
回収不能な債権をそのまま計上していたり、棚卸資産に不良在庫が含まれていれば、実際には安全性が低下していることもあります。
流動資産と流動負債を活用するときのポイント
流動比率を用いるときは、成長性を測る他の指標と併用したり、債権の回収可能性や在庫評価損を適切に反映させることが大切です。
また、流動資産のうち棚卸資産を除いた「当座資産」を用いる「当座比率」を参考にするのも有効といえるでしょう。
【当座資産とは】
・現金預金
・受取手形
・売掛金
・有価証券
【当座比率の計算式】
当座資産÷流動負債×100%
業種別の流動資産と流動負債も参考に

流動比率は業種によっても傾向が異なります。そのため、業種ごとの平均値と比較することも有効です。
業種別の流動比率については、中小企業実態調査や日本政策金融公庫による小企業の経営指標調査が参考になります。
たとえば、令和5年度の中小企業実態調査から、業種ごとの流動資産と流動負債を用いて流動比率を計算すると、次のようになります。
| 業種 | 流動資産 (百万円) | 流動負債 (百万円) | 流動比率 |
| 全体 | 334,246,324 | 179,964,510 | 185.7% |
| 建設業 | 51,781,329 | 24,790,714 | 208.9% |
| 製造業 | 82,571,054 | 40,448,989 | 204.1% |
| 情報通信業 | 10,822,379 | 4,545,782 | 238.1% |
| 運輸業、郵便業 | 11,880,222 | 6,658,610 | 178.4% |
| 卸売業 | 74,466,464 | 42,399,039 | 175.6% |
| 小売業 | 29,268,718 | 19,469,158 | 150.3% |
| 不動産業、物品賃貸業 | 37,072,144 | 21,886,004 | 169.4% |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 10,280,378 | 4,495,100 | 228.7% |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 4,125,389 | 2,724,588 | 151.4% |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 7,494,798 | 4,726,540 | 158.6% |
| サービス業(他に分類されないもの) | 14,483,449 | 7,819,985 | 185.2% |
出典:e-Stat 政府統計の総合窓口|「中小企業実態基本調査」
このように業種別に比較すると、流動比率の水準が異なることがわかります。
さらに詳しく知りたい場合は、産業中分類別のデータを確認するとよいでしょう。 たとえば、情報通信業は全体で238.1%と高い流動比率を示していますが、産業中分類別に見ると、放送業(327.9%)や映像・音声・文字情報制作業(296.2%)が特に高いことがわかります。
また、日本政策金融公庫が行っている「小企業の経営指標調査」では、流動比率を含むさまざまな経営指標を一覧で確認できます。
公庫が融資した法人のうち、従業員50人未満の企業が調査対象となる点には注意が必要ですが、より詳細な産業分類での経営指標を把握することができます。
まとめ
本記事では、流動資産と流動負債とは何か、それぞれに分類される具体的な項目、そして経営分析への活用方法について解説しました。
流動資産と流動負債は、貸借対照表における企業の支払い能力や資金繰りの健全性を示す重要な要素です。両者のバランスから算出される流動比率は、安全性を判断する代表的な指標であり、120%以上を一つの目安とすることができます。
ただし、比率が高ければ良いというものではなく、資金の活用効率や資産の内容に注意する必要があります。さらに、棚卸資産を除外した当座比率や、業種別の平均値なども併せて参照することで、より実態に即した分析を意識することが大切です。
まずは、流動資産と流動負債に含まれる資産と負債の範囲をしっかり把握した上で、顧問先企業の業種の傾向を踏まえながら、企業分析や将来の資金計画に活用するとよいでしょう。
 オンライン研修・eラーニング
オンライン研修・eラーニング
e-JINZAIで
社員スキルUP!
- e-JINZAI for account(会計事務所向け)
- e-JINZAI for business(一般企業・団体向け)
- 今ならe-JINZAIを2週間無料でお試しいただけます!

税理士.ch 編集部
税理士チャンネルでは、業界のプロフェッショナルによる連載から
最新の税制まで、税理士・会計士のためのお役立ち情報を多数掲載しています。
運営会社:株式会社ビズアップ総研
公式HP:https://www.bmc-net.jp/
































