アウトソーシング型案件を受注する
<税理士がコンサルタントとして活躍するためには?④>

日沖コンサルティング事務所・代表
中小企業診断士、中小企業大学校・講師、産業能率大学・講師
日沖 健
6回に渡って税理士がコンサルタントとして活躍するためのポイントをお伝えするシリーズの4回目。今回は、アウトソーシング型案件の受注と進め方のポイントを見ていきましょう。受注する方法を紹介します。
事業計画書作成と研修は有望な受託業務
企業は、自社内のリソースでは対応できないITシステム構築・市場調査・広告宣伝・特許出願といった業務をアウトソーシングします。税理士は、すでに会計・税務関連業務を受託しているわけですが、クライアントとの緊密な関係を活かして、受託業務の範囲を経営全般に広げたいところです。
「需要の大きさと成長性」「税理士の既存業務との親和性」という2点から税理士の先生方にとくにお勧めしたいのは、事業計画書作成と研修です。このうち事業計画書作成について解説します。
大手企業、とくに上場企業は、必ず中期事業計画書と年度予算(合わせて「事業計画書」とします)を定期的に作成し、それに基づいてPDCAを回しています。一方、多くの中小企業は、事業計画書を作成していません。作っていても、売上高と経費を見積もる程度です。ただし、中小企業が不定期で事業計画書を作成することがあります。
一つは、金融機関に融資を申し込むときです。融資の申し込みでは、融資担当者に事業計画書書を作成・提出します。もう一つは、公的支援を申請するときです。補助金・助成金など公的支援の申請書に事業計画書を添付します。 税理士の中には、クライアントの資金計画や収支計画の作成をお手伝いしている方もいるかもしれませんが、事業計画書の作成にも支援を広げたいところです。
事業計画書作成のよくありがちな対応例
まず、よくありがちな悪い対応例を紹介します。メーカーの経営者と税理士の電話でのやり取りです。
先生、事業計画書を作っていただきたいのですが
そうですか。来月そちらに伺う用事があるので、相談に乗りますよ
いえ、大至急です。来週の火曜日までに作る必要があります
そんなに急ぐんですか
ええ、メインバンクに運転資金の借り増しを相談したところ、向こう3年の事業計画書を提出してほしいと言われまして…
しょうがないですねぇ。じゃあ資金繰り表をざっと作って後でお送りしますよ
いえ、資金繰り表ではなくて、事業計画書です
ああ、予想P/Lってことですね。わかりました。お任せください
助かります。ありがとうございます
確認ですが、製品ラインナップや従業員数はそんなに変わらないですよね
ええ、ただ旋盤機械が老朽化しているので、再来年には更新したいと考えています
再来年ですか。まあ先のことはどうなるかわからないし、急ぎなので、今回は考慮する必要はなさそうですね
…
という前提で、今年の売上高や経費を適宜引き伸ばして、予想P/Lを作っておきますよ。少しお待ちください
税理士は、以下の2つの前提を置いて収支を計算しました。
- 売上高が年3%伸びる
- 人件費は賃上げで年1%増えるが、減価償却費・補修費は減少するので経費全体はほぼ横ばい
その結果、売上高・営業利益・経常利益が着実に増え続けるという、増収増益の素晴らしい予想P/Lができ上がりました。
その場しのぎの仕事でも大丈夫?
この事業計画書(という名の予想P/L)でクライアントがメインバンクから追加融資を受けられるかどうかは、メインバンクの姿勢次第です。
もしメインバンクの融資担当者から経営者に、「稟議書を上申するにあたり事業計画書を添付する必要があります。形式的なもので構いませんから、提出してください」と依頼されていたなら、このようなその場しのぎの仕事でも追加融資は実現するでしょう。
しかし、融資担当者が提出された事業計画書を元に返済可能性などをしっかり吟味した上で稟議書を上申するというなら、追加融資は実現しない可能性が高いでしょう。
この事業計画書には、次のような問題があるからです。
- 会社をどういう方向に発展させたいかという経営者の意思が感じられない。
- 外部環境の変化や自社の強み・弱みを踏まえていない。
- 旋盤機械の更新投資が盛り込まれていないなど、経営実態と異なっている。
- 売上高が年3%伸びるという根拠(売上高を増やすための方策など)が示されていない。
- 設備が老朽化しているのに補修費が減るというのは非現実的。
- 順調に利益が増えるなら、運転資金の借り増しは必要ないのでは、という疑問が湧く。
ある程度の経験がある融資担当者なら、こうした問題点のいくつかに気づいて「“鉛筆なめなめ”のいい加減な事業計画書だな」と不信感を持ちます。場合によっては追加融資をしないだけでなく、この経営者を「要注意人物」とみなすかもしれません。
事業計画書作成の留意点 ① ルールを守る、作法に従う
融資なら金融機関が、公的支援なら公的機関が、事業計画書の記載事項・書き方・提出方法などを指定しています。また、各機関によって独特の作法があったりします。
どんなに素晴らしい中身の事業計画書でも、こうしたルールを守り、作法に従わないと、申請が受理されず、門前払いになったりします。とくに国民の税金を使う公的機関は、ルールに厳格です。
税理士はこうしたルールや作法をしっかり勉強、確認し、そこから逸脱したりすることがないように、細心の注意を払う必要があります。
事業計画書作成の留意点 ② 経営者の思いが第一
事業計画書には色々な項目を盛り込む必要があります。あれもこれもと検討するうちに、つい重要なポイントを見失いがちです。「これだけは伝えたい!」というメッセージを明確にする必要があります。
事業計画書で明確に伝えたいメッセージは、案件の内容によって異なります。が、会社をどのように発展させたいのか、事業計画書で何を実現したいか、という経営者の思いが何より重要です。大事な箇所については、税理士があまり加工せず、経営者の生の声を紹介すると良いでしょう。
事業計画書作成の留意点 ③ 保守的・現実的に
経営者は「融資を受けたい!」「補助金を獲得したい!」と強く思うと、どうしても「(融資/補助金を受けて)この設備投資をすれば、わが社はこんなに発展します!」とバラ色の絵を描こうとします。
しかし、経験のある金融機関や公的機関の担当者は、「そんなに上手くいくはずがないだろ」と冷めた目、疑いの目で見ています。あまりにも現実離れした計画だと、事業計画書を信用してもらえないだけでなく、「噓つき経営者」と不信感を持たれてしまいます。
むしろ、保守的・現実的な計画を作り、リスク要因を洗い出し、厳しい状況をどう打開していくのか、リスク要因にどう対応するのかを率直に伝える方が、「現実を直視できる沈着冷静な経営者」という高い評価を得ることができます。
事業計画書作成の留意点 ④「なぜ?」のロジックを大切に
金融機関や公的機関の担当者はたくさんの企業を担当しているので、個々の会社の内容をそんなに深く知っているわけではありません。経営者は予想P/Lを提出して「一丁終わり」と考えがちですが、担当者は数字の羅列だけでは判断に困ってしまいます。
事業計画書では、売上高・利益がなぜ増えるのか、なぜ減るのかをロジカルに説明する必要があります。
事業計画書作成の留意点 ⑤ 見栄えが良すぎる事業計画書は逆効果
世間には事業計画書作成の代行業者がたくさんあり、こうした業者に作成を依頼すると、5フォース分析、バリューチェーン、ポジショニングマップといった経営戦略の様々な技法を駆使した見栄えの良い事業計画書を作ってくれます。
経験のある金融機関や公的機関の担当者は、こうした事業計画書を見て、「これは代行業者を使ったな」と見破ります。場合によっては、「自分が理解していない資料を平気で出す、不誠実な人物」という厳しい評価になってしまいます。
分不相応に見栄えが良すぎる事業計画書は、逆効果。留意点②の通り、経営者の思いを丁寧に伝えるようにしましょう。
プロジェクト型コンサルティングに繋げる
多くの場合、融資や補助金を獲得することが目的になってしまって、目的達成ですべてが終わり、せっかく作った事業計画書が実際の経営に生かされていません。
コンサルタントがクライアントを支援する最終的な目的は、融資や補助金を獲得することではありません。クライアントが自律的な経営をし、永続的に発展することです。事業計画書を作って終わりでなく、経営の計画に基づいてしっかりPDCAを回すという状態になるよう支援したいところです。
税理士は、事業計画書作成から踏み出して、毎年の年度予算や3年に1度の中期事業計画書の作成や計画に基づいて活動する組織づくりでも貢献することができます。 クライアントのメンバーと一体となって会社の計画作りや組織改革をするプロジェクト型コンサルティングについては、次の第5回で紹介します。
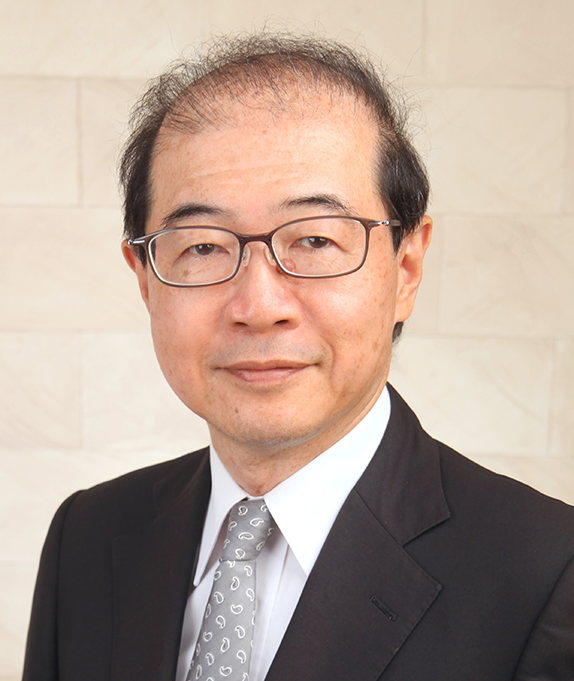
日沖 健
日沖コンサルティング事務所・代表
中小企業診断士、中小企業大学校・講師、産業能率大学・講師
1965年愛知県生まれ
慶応義塾大商学部卒、Arthur D. Little 経営大学院修了MBA with Distinction
日本石油(現・ENEOS)勤務を経て2002年より現職
経営戦略のコンサルティングと経営人材育成の研修を行う。また、中小企業大学校・中小企業診断士養成課程で後進のコンサルタントの育成にも注力している。
東洋経済オンラインに記事連載中、テレビ出演多数
著書(コンサルタント関係)
『税理士消滅時代を生き抜く ―コンサルタントへの進化戦略』
『コンサルタントを使って会社を変身させる法』
『コンサルタントが役に立たない本当の理由』
『中小企業診断士のリアル』
『中小企業診断士の独立開業のリアル』
『企業内診断士のリアル』






