AI全盛時代に備えよ!
集約したデータ駆使し一般事業への参入目指す 若き税理士経営者の戦略に迫る Vol.2

税理士法人SoLabo 代表社員 手島 春樹
リスクとどう向き合うか
AIが抱える根本的な欠点とは?
一方で、AIが間違った回答を導く恐れについては、どのように評価されていますか?
AIは、完璧ではありません。いわゆる「ハルシネーション」と呼ばれるように、AIには、分からないことを分からないといえず、結果として嘘をついてしまうという欠点があります。質問をしても、「法人税法420条によると・・・」のように、存在しない条文を挙げて回答するようなことも実際にあるのです。
もちろん、そういう事態を避けるための取り組みも行っています。データを充実させ、整理しておくというのも一つの手段です。特にGemsを用いる際には、AIが参考にする情報や資料を少しでも拡充し、それらを顧問先ごとのフォルダー内に正確に格納しておくことが正しい回答を導くのに非常に役立ちます。
ある顧問先のフォルダーに別の顧問先の情報が入ってしまうと、AIが情報を探せなくなってしまうからです。あるいは、ものすごい分量のプロンプトを書いて、AIの動きをガチガチに制限することで、間違った情報を参考にしないよう働きかけるやり方も存在します。弊社ではこれらの取り組みを通じて、「AIが自走できる環境」を実現したいと考えています。
ただそれでも、AIが絶対に間違いを犯さないとはいい切れません。その点は留意する必要があります。

既に記帳代行はAI-OCRを通じて自動で進めていると仰っていましたが、そうしたAIが持つリスクにどんな対策をとっているのでしょうか?
記帳というのは極めて重要な業務で、少しのミスが会計事務所の信用問題に関わる恐れもあります。当然ながら、細心の注意を払わなければなりません。一方で、記帳は単調な業務の繰り返しだという側面も否めませんので、できれば自動でサクサク進めていきたいというのが本音でもあります。正確さとスピードを両立し、さらにいえばコストも抑えたい。そうした理想に近づくために弊社が行なっているのが、記帳業務の一部の外部委託です。顧客のデータが、クラウド会計ソフトに取り込まれた後の業務は弊社側が担いますが、それ以外の工程やチェックは専門の会社にお任せしています。
先ほどもお話しした通り、データは基本的に自動で流れていくのですが、領収書やレシートをスキャンしたり、それら原本とスプレッドシートのデータを突き合わせて齟齬がないかどうかを確認したりするには、どうしても人力が必要になります。委託しているのは障がい者の就労支援を行っている会社で、「SoLabo専用レーン」のようなスキームを組んでもらっています。ひたすらスキャンを行う方、データをチェックする方など、利用者様 の適性に合わせて作業を行っていただいています。一つ一つの細かなデータを苦にすることなく素早くチェックして下さるので、本当にありがたく思っています。
外部委託というのは、余計にコストがかかる気がするのですがいかがですか?
確かにコストはかかりますが、それでも、データのチェックを無理に内製化するというのはあまりにも非効率です。チェックしなければいけないデータの量は膨大です。それを自社の人員だけでやり切るには、それこそ、それ相応の時間とコストを覚悟しなければなりません。もちろん、他の業務の手も止めなければいけない。チェック業務に不慣れであれば、誤りを見落とすリスクも出てきます。そうであれば、外部委託するというのは、むしろ自然な選択だと思います。加えていえば、コストに関しても、内製化するよりもずっと低い水準に抑えられています。
AIの性質を正しく理解することでリスクに対応するのは可能です。そこに十分向き合わずに、「AIは間違える」という先入観だけで従来通りの業務を続けていくのというのはあまりにもナンセンスだと思います。
会計業界はどう変わるべきか
キーワードは「一般事業」
お話を伺っていると、やはり、AIの進化で会計事務所の業務は大きく変わらざるを得ないのだろうという印象を受けました。

現在の申告納税制度がなくならない限り、会計業界や税理士自体がなくなることはないでしょう。しかし、「会計事務所」という枠組みに固執している限りは、売上は一向に伸びていかないと思います。ここまでお話ししてきた通り、記帳代行はもちろん、高付加価値に分類される業務でさえも、AIを活用できる領域がどんどん広がってきているからです。会計事務所の従来の業務だけを行っていては、この業界は間違いなく縮小してしまうでしょう。
業界の明るい未来のために、どんな取り組みが求められると思いますか?
AIの進化は止められないですし、むしろ、そうした動きは積極的に受け止めるべきです。業務の効率化が実現するというのは喜ばしいことですし、それによって単価が下がるというのも当然の成り行きです。
では、会計事務所が売上を伸ばし、規模を拡大していくにはどうすればいいのか。私は、会計事務所も他業種の一般事業に積極的に進出するべきだと考えています。極端な話、業種は何でも構わないのです。会計業界の従来の常識にしがみつき続けてもしょうがない訳で、もっと柔軟な発想で総合的に売上を上げに行くための施策に力を入れるべきです。会計事務所は、幸いなことに様々な業種の顧問先と付き合いがありますから、経営の知見を得ることもそう難しくないと思います。
これからの会計事務所は、一般事業が「主」、税務会計が「従」へと変わらざるを得ないのではないでしょうか。売上を伸ばしたいと考えている事務所のトップは、早急に、こうした発想に転換するべきだと思います。
会計業界に求められる人材の質というのも、変わってくる気がします。
優秀な人材に振り向いてもらうには、「高待遇」を施すというのが基本になります。「楽しくて、雰囲気がいいからうちで働いて下さい」という誘い文句は、もはや通用しません。経営者は、高い給与を支払うからこそ優秀な人材が集まってくる、という現実から目を逸らしてはならないのです。その代わり、従業員にはしっかりと成果を出してもらう。その成果が、巡り巡って給与にも反映されるというような好循環を築いていかないと、他業界との人材獲得競争には勝てません。
その上で、どんな人材を「優秀」と定義するのかが重要になってきますが、私は、コミュニケーション能力の高い方こそ「優秀」だと、会計業界でも考えられるようになると見ています。資格の有無すら関係ありません。ざっくばらんに申し上げて、「元気で愛嬌があって、運動部っぽい」方が求められるようになるのではないでしょうか。専門知識は後からいくらでもついてくる訳で、一般事業会社と同じく、人懐っこく、誰にでも可愛がられる方が好まれるようになると思います。
そういう意味でも私たちには、会計業界だけに目を向けるのではなくて、常に、一般の事業会社と比較をしながら戦っていくという心構えが求められるようになるでしょう。
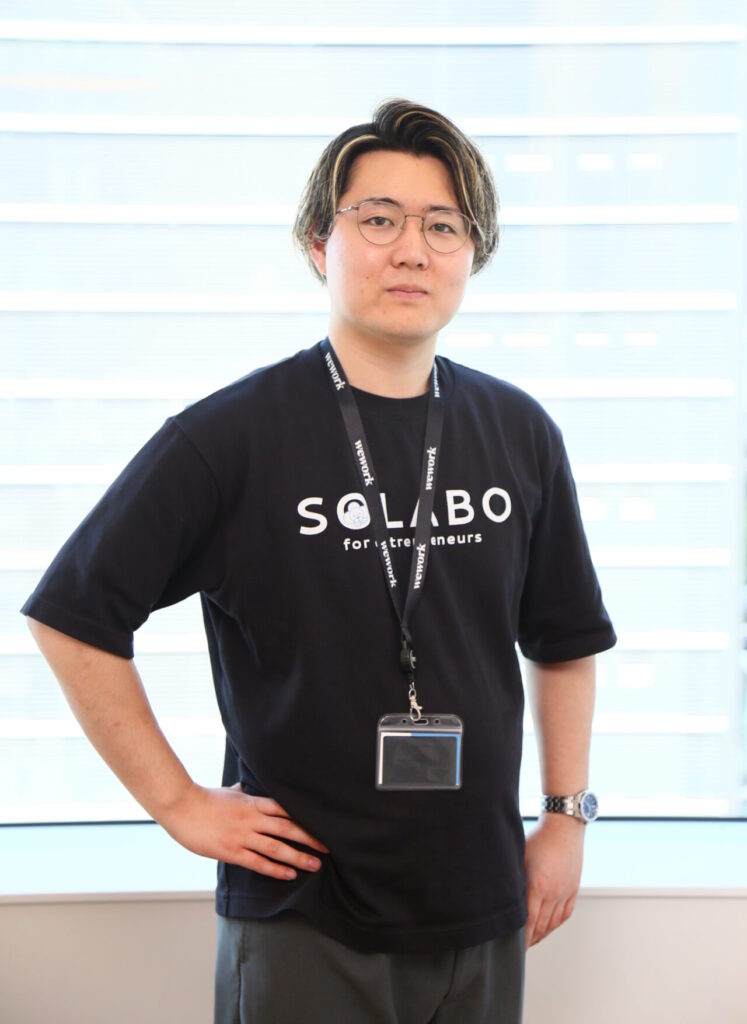
貴社の経営も、優秀な人材を集めて、一般事業に乗り出すという方向性になっていくのでしょうか?
将来的には、そこを目指していきたいです。
既に触れたように、会計事務所には、様々な業界の経営に関するデータが集まってきます。今は、そうしたデータをできる限り多く集め、足元を固める段階です。そして今後は、集まったデータを分析するフェーズに移行していきます。その結果をいかして、将来的には一般事業に挑戦していきたいと考えています。会員制のバーなのか、飲食店なのか旅館なのかは分かりませんが、経営者の方たちが交流できる場を作りたいです。
弊社は、税理士法人だけで終わるつもりはありません。一般事業会社と対等に戦って、売上が100億円とか、200億円まで成長できる会社へと飛躍していきたいです。
| プロフィール |
|---|
| 株式会社SoLabo/税理士法人SoLabo 取締役COO/代表社員 公認会計士・税理士 手島 春樹 太陽有限責任監査法人にて、小売業、製造業、建設業、美容業、IT系及び音楽業界等幅広い業界の会計監査に従事。顧客の東証グロース市場への新規上場や、不正案件対応を経験。 2023年7月から株式会社SoLaboに入社。2024年8月から同社 取締役COOに就任。事業部再編やインサイドセールス立ち上げ等の組織づくりからCRMを活用したデータベースの利活用、株式会社での経営層経験を基にした全体最適化コンサルティングを得意とする。顧客ニーズに応えるため、税務サービス提供を目的とし、2025年6月に税理士法人SoLaboを立ち上げる。 |






