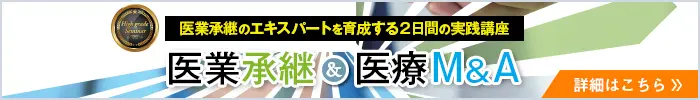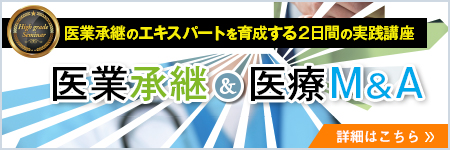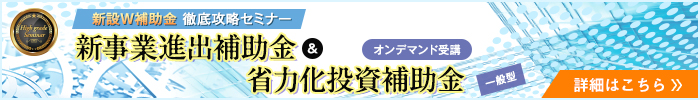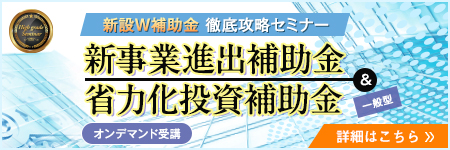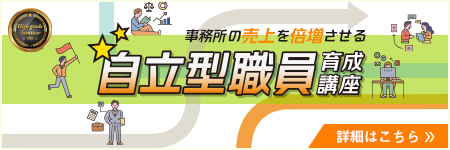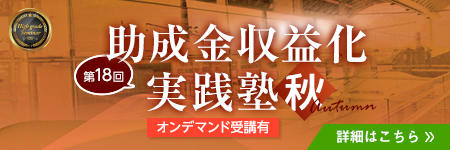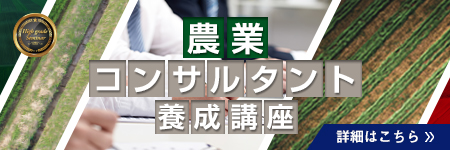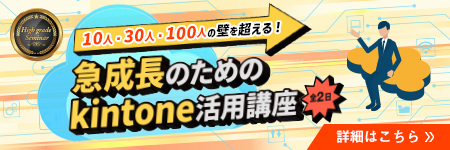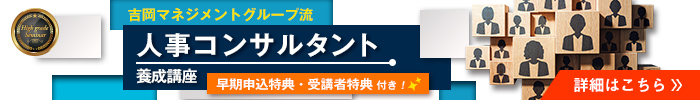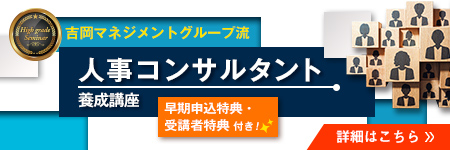税理士業界が注目した 今月の気になる税務トピック Vol.37

『税理士のための相続税Q&A 小規模宅地等の特例』など多数の著書を持ち、研修講師としても活躍する白井一馬先生が、税理士業界注目のニュースや気になる話題をピックアップ。独自の視点も交えながら、コンパクトに紹介します。
※本記事は、会報誌『BIZUP Accounting Office Management Report』vol.141(2025.7)に掲載されたものです。
白井税理士事務所 所長・税理士
白井 一馬 先生
京都の味噌会社の高額役員報酬事件
京都の著名な松井味噌のグループ企業において高額役員報酬が否認された事件。最高裁は上告を退ける決定を出した。
どのような事件だったか。松井味噌のグループ企業である京醍醐味噌がベトナム新規事業に進出するにあたり、社長の実弟が赴任し経営全般を担う予定になっていた。しかし、ベトナムにおける個人所得の課税関係が当初見込んだものとは違うとの情報を入手したため、ベトナム新規事業の実施を留保することとなった。
結局ベトナム事業の収益はゼロであるにもかかわらずその後取締役会において、実弟の給与を月額2億5,000万円とする旨議決し、4か月間に合計10億円の給与を支払った。さらにこの期においては保有株を売って事業資金約20億円を確保し投資有価証券売却益が計上されている。
税務調査では2013年から2016年の4年間、社長の松井健一氏と実弟に支払われた役員報酬21億5,100万円のうち、約18億3,956円分を「不相当に高額」と認定し、約3億8,500万円の課税処分が行われている。
そもそもどのような節税を想定していたのか分からない部分があるが、税負担にメリットがないことを理由に新規事業を中止したのに、株の売却益を相殺するだけの役員報酬を払った、こうなると否認されるのは当然で、東京高裁に続き最高裁でも結果は変わらなかった。
相続後の債権放棄
実務の教材として、他山の石としてのチェックが欠かせない懲戒処分事例(令和7年6月15日現在)。散見されるのが相続開始後の債権放棄書の作成。
関与先法人の前代表者を被相続人とする相続人の相続税の申告に当たり、被相続人が会社への貸付金を放棄したとする虚偽の確認書を相続開始後に作成、相続財産から除外することにより、相続税の課税価格を圧縮した真正の事実に反する申告書を作成したとされる事例が公表されている。
なぜ相続後の放棄が露呈したのだろうか(パソコンを調べたのか?)。会社は債務超過だったのか資産超過だったのか。バックデートが危険なことは税理士なら分かるはずで、債権の評価の問題にできなかったのか。生前に放棄をアドバイスせず納税者から苦情があったのだろうか。それとも税理士が役に立とうとして知恵に溺れたか。
調査官は死亡後の放棄を疑うと税理士は認識すべきだろう。可能な限り、相続前の法人の決算書に放棄が反映されているようにしたいところだ。
所得税行為計算否認を巡る事件で国が高裁で逆転勝訴
大阪地裁で納税者勝訴となっていたサブリースの事件が、大阪高裁で逆転して納税者敗訴になったそうだ(大阪高裁令和7年4月25日)。
個人オーナーが同族会社に一括賃貸するいわゆるサブリースについて、個人オーナーが、賃借人から受け取った転貸家賃の54%から60%しか受け取っていなかったところ、所得税法上の同族会社に係る行為計算否認が発動した事件だ。
税務署は適正賃料の計算において20%程度の利ザヤを認めて更正処分したものの納税者が納得しなかったことで訴訟になったのだが、当然の判決だと思う。裁判所は6%程度が妥当としている。

白井 一馬
しらい・かずま/石川公認会計士事務所、 税理士法人ゆびすいを経て独立。『顧問税理士のための相続・事業承継スキーム発想のアイデア60』 『一般社団法人一般財団法人信託の活用と課税関係』『一般社団法人・信託活用ハンドブック』ほか 著書多数。